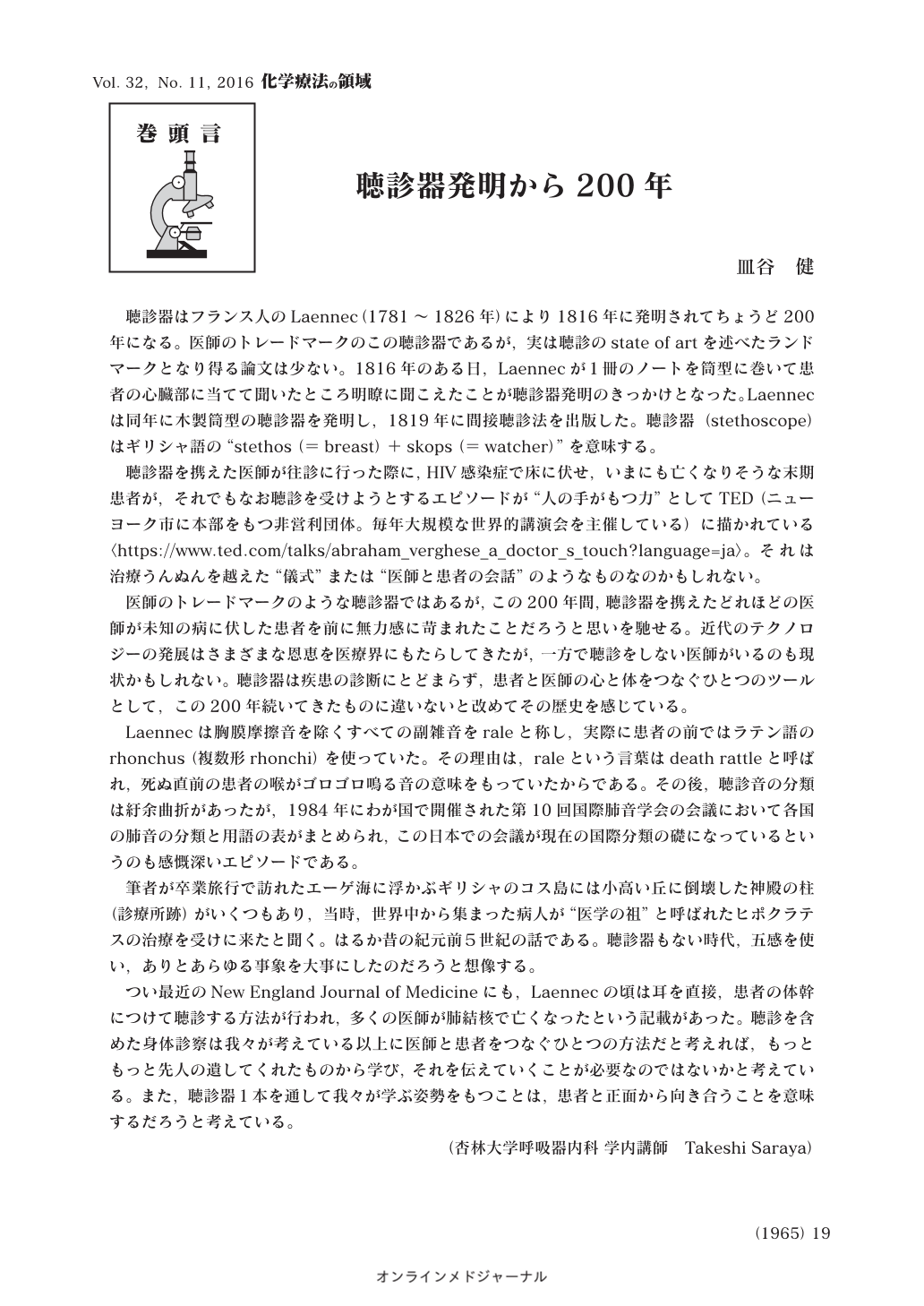- フリーアクセス
- 文献概要
- 1ページ目
聴診器はフランス人のLaennec(1781~1826年)により1816年に発明されてちょうど200年になる。医師のトレードマークのこの聴診器であるが,実は聴診のstate of artを述べたランドマークとなり得る論文は少ない。1816年のある日,Laennecが1冊のノートを筒型に巻いて患者の心臓部に当てて聞いたところ明瞭に聞こえたことが聴診器発明のきっかけとなった。Laennecは同年に木製筒型の聴診器を発明し,1819年に間接聴診法を出版した。聴診器(stethoscope)はギリシャ語の“stethos(=breast)+skops(=watcher)”を意味する。 聴診器を携えた医師が往診に行った際に,HIV感染症で床に伏せ,いまにも亡くなりそうな末期患者が,それでもなお聴診を受けようとするエピソードが“人の手がもつ力”としてTED(ニューヨーク市に本部をもつ非営利団体。毎年大規模な世界的講演会を主催している)に描かれている〈https://www.ted.com/talks/abraham_verghese_a_doctor_s_touch?language=ja〉。それは治療うんぬんを越えた“儀式”または“医師と患者の会話”のようなものなのかもしれない。 医師のトレードマークのような聴診器ではあるが,この200年間,聴診器を携えたどれほどの医師が未知の病に伏した患者を前に無力感に苛まれたことだろうと思いを馳せる。近代のテクノロジーの発展はさまざまな恩恵を医療界にもたらしてきたが,一方で聴診をしない医師がいるのも現状かもしれない。聴診器は疾患の診断にとどまらず,患者と医師の心と体をつなぐひとつのツールとして,この200年続いてきたものに違いないと改めてその歴史を感じている。 Laennecは胸膜摩擦音を除くすべての副雑音をraleと称し,実際に患者の前ではラテン語のrhonchus(複数形rhonchi)を使っていた。その理由は,raleという言葉はdeath rattleと呼ばれ,死ぬ直前の患者の喉がゴロゴロ鳴る音の意味をもっていたからである。その後,聴診音の分類は紆余曲折があったが,1984年にわが国で開催された第10回国際肺音学会の会議において各国の肺音の分類と用語の表がまとめられ,この日本での会議が現在の国際分類の礎になっているというのも感慨深いエピソードである。 筆者が卒業旅行で訪れたエーゲ海に浮かぶギリシャのコス島には小高い丘に倒壊した神殿の柱(診療所跡)がいくつもあり,当時,世界中から集まった病人が“医学の祖”と呼ばれたヒポクラテスの治療を受けに来たと聞く。はるか昔の紀元前5世紀の話である。聴診器もない時代,五感を使い,ありとあらゆる事象を大事にしたのだろうと想像する。 つい最近のNew England Journal of Medicineにも,Laennecの頃は耳を直接,患者の体幹につけて聴診する方法が行われ,多くの医師が肺結核で亡くなったという記載があった。聴診を含めた身体診察は我々が考えている以上に医師と患者をつなぐひとつの方法だと考えれば,もっともっと先人の遺してくれたものから学び,それを伝えていくことが必要なのではないかと考えている。また,聴診器1本を通して我々が学ぶ姿勢をもつことは,患者と正面から向き合うことを意味するだろうと考えている。