- 有料閲覧
- 文献概要
- 1ページ目
- 参考文献
「痛み」に関して近年,国際疼痛学会(International Association of the Study of Pain:IASP)を中心に3つの大きな変革があった。1つ目は2016年の痛みの新しい機序分類である「痛覚変調性疼痛(nociplastic pain)」という概念の提唱である1)。これまでに痛みの機序としては侵害受容性疼痛(nociceptive pain)・神経障害性疼痛(neuropathic pain)の2つだけであり,両者で説明できない痛みは心理社会的痛みとされ,あたかも心因性の問題が主であるような印象を与えてきた。実際には多くの研究で中枢神経系の可塑性変化が引き起こされ痛みが惹起されていることが知られており,それを痛覚変調性疼痛という第3の痛み機序分類として表現できたことは非常に大きな変革である。2つ目は2020年に痛みの定義が40年ぶりに改定されたことである2)。痛覚変調性疼痛を含む痛みを反映して「実際の組織損傷もしくは組織損傷が起こり得る状態に付随する,あるいはそれに似た,感覚かつ情動の不快な体験」と定義された。初見では理解が難しい表現であるが「組織損傷が起こり得る状態に付随する,あるいはそれに似た」が痛覚変調性疼痛を含む表現として示されており,定義にも神経の可塑性変化を含ませることができた(表1)。3つ目は2022年の国際疾病分類(International Classification of Diseases 11th revision:ICD-11)に慢性疼痛の分類コードが初めて加えられ,慢性一次性疼痛・慢性二次性疼痛と分けられたことである3)。慢性一次性疼痛は痛覚変調性疼痛を主に含んだ疾患分類である点が上記に続く流れである。ICDは世界保健機関(World Health Organization:WHO)が作成する国際的な疾病の分類で,世界の疾病・健康関連問題の動向の把握などに用いられているため,慢性疼痛の疾患としての認識を世界的に広めるきっかけとなり慢性疼痛診療の発展に寄与すると考える。
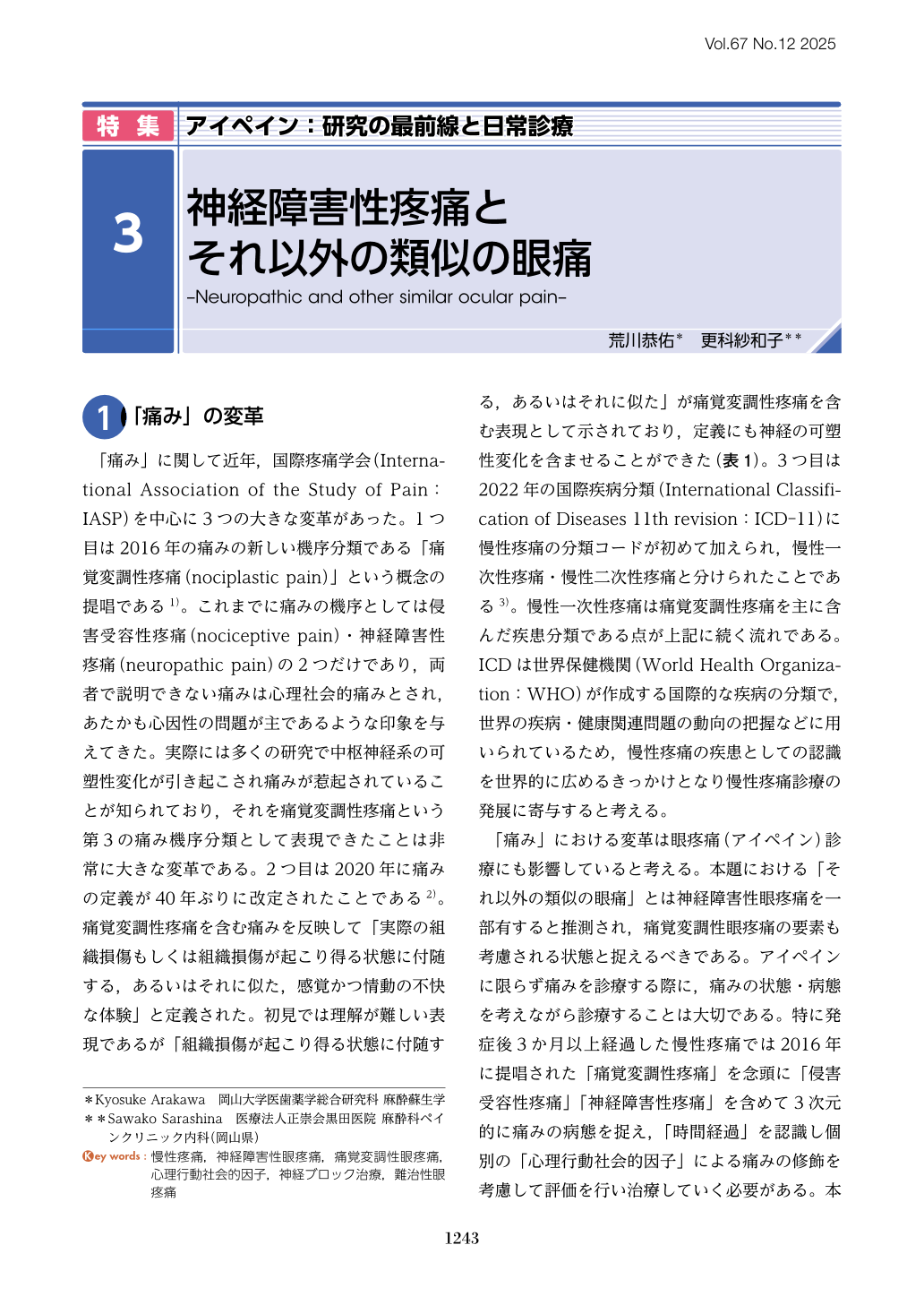
Copyright © 2025, KANEHARA SHUPPAN Co.LTD. All rights reserved.


