実験講座
生体活性アミンの組織化学
田中 千賀子
1
,
藤原 元始
1
1京都大学医学部薬理学教室
pp.284-294
発行日 1971年12月15日
Published Date 1971/12/15
DOI https://doi.org/10.11477/mf.2425902908
- 有料閲覧
- 文献概要
- 1ページ目
Ⅰ.はじめに
生体活性アミンは極微量で著しい生理作用を示すものが多く,種々の生理機能変化に対応する組織内アミンの量的変化を求めようとすると,多くの方法論的困難ないし限界に直面する。たとえば,視床下部の視索前野には温熱刺激に対応して発火興奮する温受容細胞があり,脳室や前視床下部へSerotonin(5HT)やNoradrenaline(NA)を注入すると体温が変化するという事実から,前視床下部に分布する神経からの生体活性アミン遊離にょつて,体温は中枢性に調節されているとする考えがある1)。ところが,実際発熱ウサギの視床下部の5HTやNAを化学的に定量分析するとその変化はわずかである2)。これは視床下部にある特定機能単位の神経から遊離する微量の5HTやNAの変化を知るのに,ウサギ視床下部の5HTやNA量を全体として測定するというやり方に方法論的な限界があるわけである。また,細胞下レベルでの生体活性アミンの存在形式と遊離機構を研究するのには通常遠心分画法により細胞成分を分離する方法が行なわれ,神経終末部の興奮伝達に関する数多くの知見が得られてきた。しかし,神経終末部と神経細胞体各々における生体活性アミンの生合成と存在様式の検討,アミンの軸索形質内輸送,さらに機能単位別の神経細胞集団での生体活性アミンの相互関係を知るには電子顕微鏡および組織化学など形態学,細胞化学的手法の導入が必要であつた。
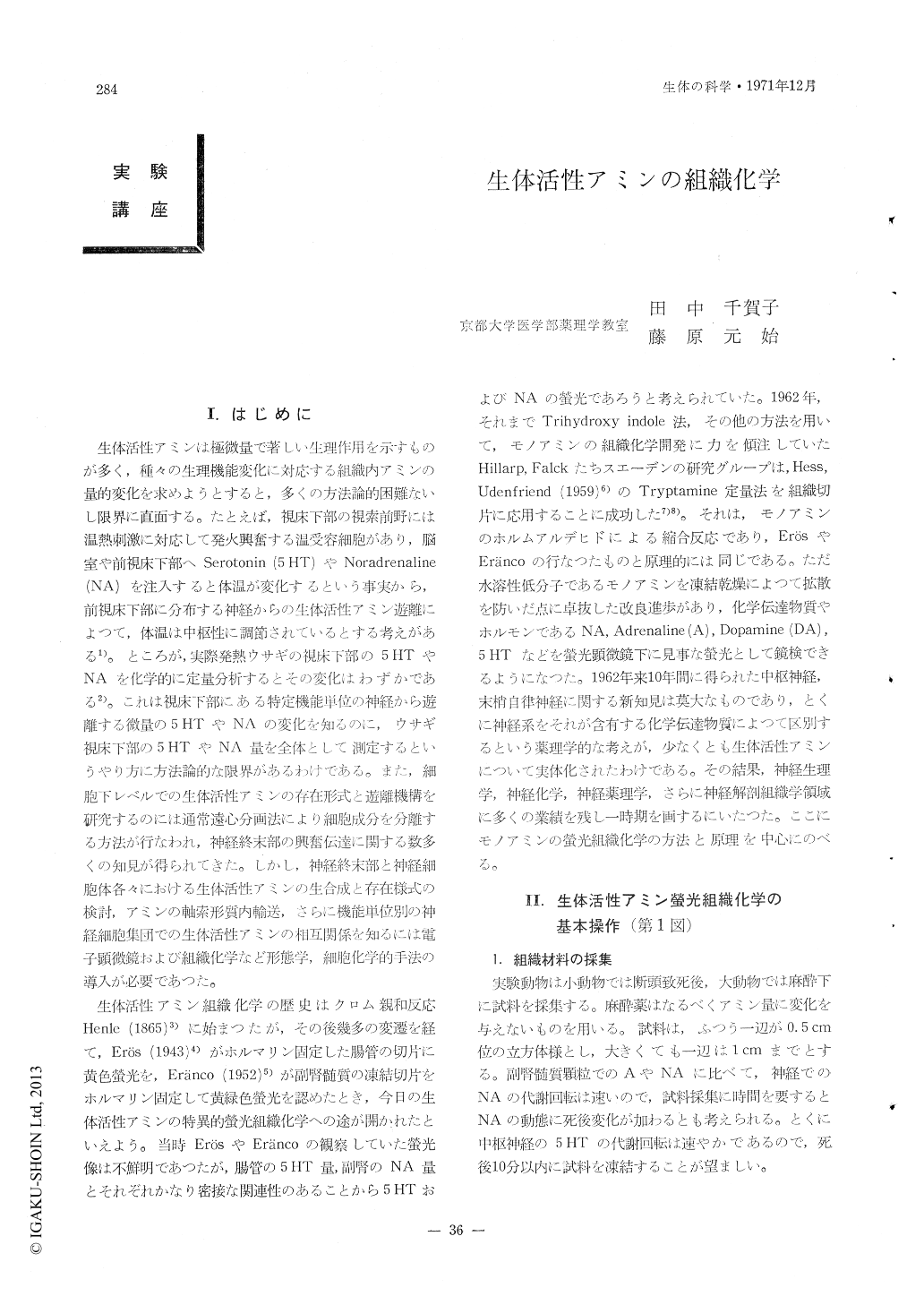
Copyright © 1971, THE ICHIRO KANEHARA FOUNDATION. All rights reserved.


