- 有料閲覧
- 文献概要
- 1ページ目
- 参考文献
- サイト内被引用
はじめに
わが国は多死時代を迎え,よりよい看取りのあり方への関心が一層高まっている。人々の穏やかな死を支えるために,そして,人生を全うする死(清水,2013)を支えるために,ケア提供者は看取りの場でどのようなかかわりをしていけばよいのだろうか。それを解き明かす重要なキーの1つが,「死亡診断書」であると考える。
人の死に際しては,わが国では医師法に基づいて死亡診断書を作成する医師が,24時間態勢で立ち会う形がとられてきた。しかしながら,近年,介護保険施設や在宅療養の場などにおける昼夜を問わない立ち会いは,医師に大きな負担がかかるため,状態の急激な変化や事故,虐待などによる死の場合は除外して,病状のこれまでの経過から確実に予想される死(以下,予想される死)については一部,看護師による死亡確認が行なわれている。
石川(2011)は,ある県において訪問看護師の臨終時の対応について調査した結果,回答のあった79名のうち,20名(26.7%)が,医師の立ち会いがないときに死亡確認を行なっていたと報告している。しかし,一方では,死の三徴候がみられた後,医師の死亡確認を待つために患者に触れずに医師を待った経験があったのは36名(45.0%)あったことも報告されている。対象の臨終の場を病院や介護施設に広げると,日本の看護職による死亡確認は,法的位置づけが明らかでなく,また,看護基礎教育においても取り扱われていないため,死亡が確実であっても,医師を待つことが一般的な現状にあることが推察される。
死亡確認に関する法律について川越(2008)は,医師と看護師が常時身近に存在することを前提として整備されてきたそれまでの法律は,在宅という新しい環境を十分カバーしていないため,結果的にサービスを受ける患者が不利益をこうむり,携わる医療者に過度の負担がかかることになったと指摘しているが,これらの不利益や負担は,地域での看取りの普及が進まない大きな要因となっていると考える。
予想される死における看護職による死亡確認は,医師の負担軽減をもたらすことは当然であるが,看取りのプロセスを安寧な形で進めることにも深くかかわってくる。坂口ら(2008)はホスピスで家族を亡くした遺族の心残りに関する研究を行ない,別れの言葉が言えなかった,あるいは聞けなかったことが死別後の心残りとなると報告している。在宅やグループホームなどの介護保険施設において,看取り態勢の問題から,死亡直前に救急病院に搬送されたりすることは,慌ただしさのなかで,別れの言葉が言えない状況を生み,遺族の心残りにつながる。したがって,看護職による適切な死亡確認は,家族とのこれまでの信頼関係が途切れない形でのケア環境を維持でき,対象者を,より安らかな永眠に導きうると考える。
それでは,わが国で一部行なわれている看護師による死亡確認は,それぞれの看取りの技術や知識を背景に,理念をもって行なわれているのであろうか。それとも単に医師に負担がかかるからというだけの理由で行なわれているのであろうか。
スウェーデンにおけるホスピス・緩和ケアは,生活世界ケア(齋藤,2012)として報告されるなど,北欧ケアと表現されて,近年一層,その思想性が注目されている。筆者らは2012年に同国を訪問し,ナーシングホームを視察した際に,職員のRegistered Nurse(以下,看護師)から,予想される死の場合は,夜間の死亡確認は自分たちの職種によって行なわれるのが一般的であるが,それは当然であると思っているとの説明を受け,実践の理念的背景に関心を抱いた。そして,スウェーデンのend-of-life careシステム,とりわけ,看護師による死亡確認の現状,アセスメント方法,その医行為の背景にある理念・しくみなどについて確認し,日本の看護の看取り教育システムの再構築を検討する必要があると考えた。
そこで筆者らは,「予想される死への看護職による死亡確認の教育プログラム開発」を研究テーマとして,スウェーデンにおけるend-of-life careシステムからの示唆を得るために,2013年同国を再訪問した。そして,前述の死亡確認の現状,理念,および法的環境などについて,緩和ケア実践の現場と教育の場にいる看護職にヒアリングを実施したので,今回は前者に焦点を当てて報告したい。
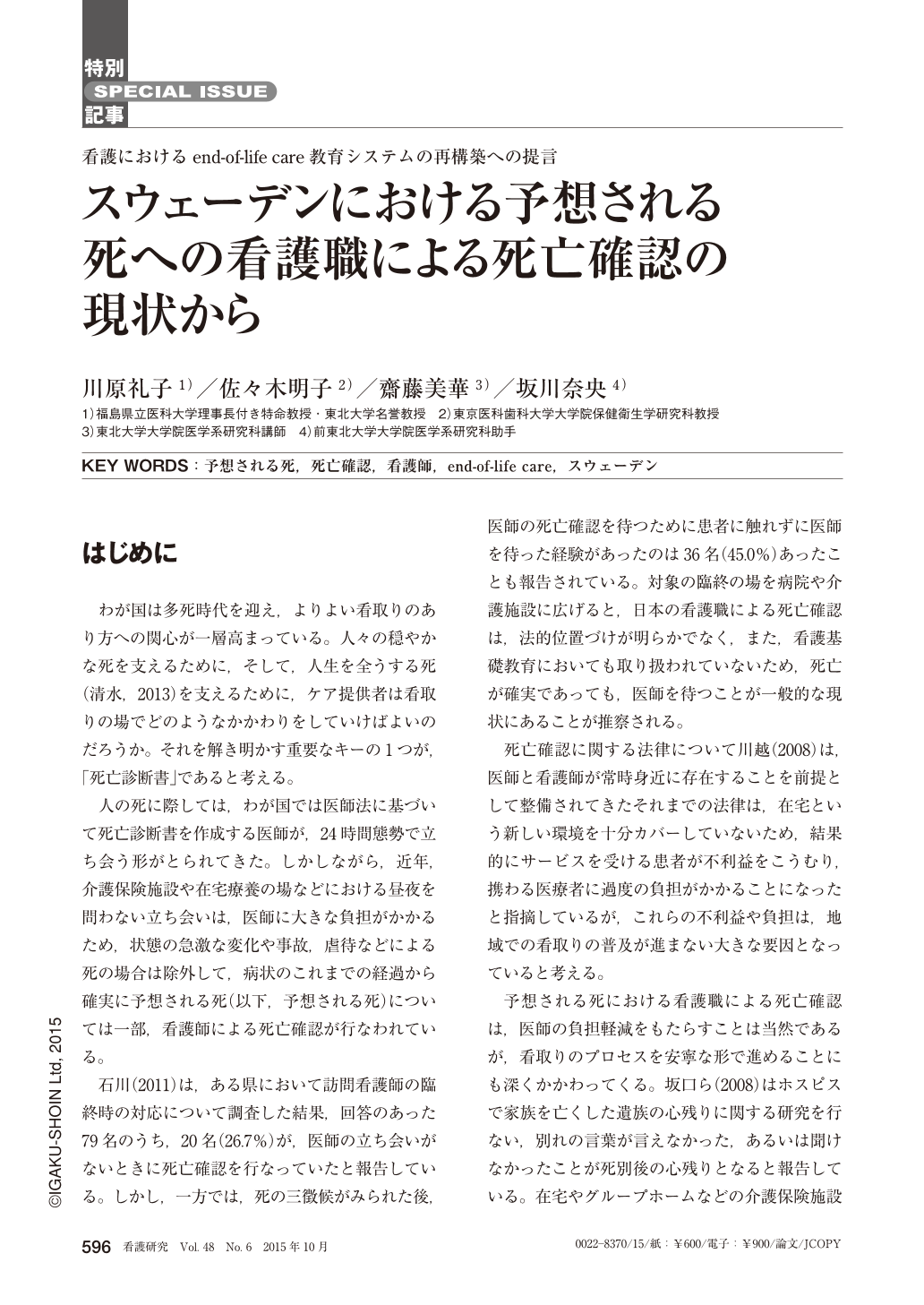
Copyright © 2015, Igaku-Shoin Ltd. All rights reserved.


