特集 患者の死をみまもって
家
松本 こずえ
pp.265-267
発行日 1980年3月1日
Published Date 1980/3/1
DOI https://doi.org/10.11477/mf.1661918903
- 有料閲覧
- 文献概要
- 1ページ目
ちょうど10年ほど前,1960(昭和45)年のころ,その地方都市の郊外に近い地にある公立病院の,深い植え込みの奥にある古い木造建ての結核病棟,そこの婦人病棟はそのころでもほとんど満床であった.
戦後減少した結核であったが,病棟が縮少されたことと,そのころの患者のほとんどが中高年者で,過去に幾度も軽快退院,そして再入院というようなことを繰り返した患者さんで,長期療養者になっていたからである.そうした婦人患者の多くは,もはや帰りたくとも帰るべき家を持たないような人びとでもあった.ある婦人は,子供もなん人もあるのにすでに離婚されていたり,ある人は,籍はつながっていてもその夫の家には自分に代わる別な婦人が座っていたり,また,家も家族もあっても,元気いっぱいの姑が居て家の一切のこと,孫のことなど取りしきっているので,もどって行っても働けない体では,だれにも相手にもされなかったり,それよりもそのころの結核に対する偏見には根強いものがあり,いわゆる肺病やみは安心して座れるような場はないのが常であった.
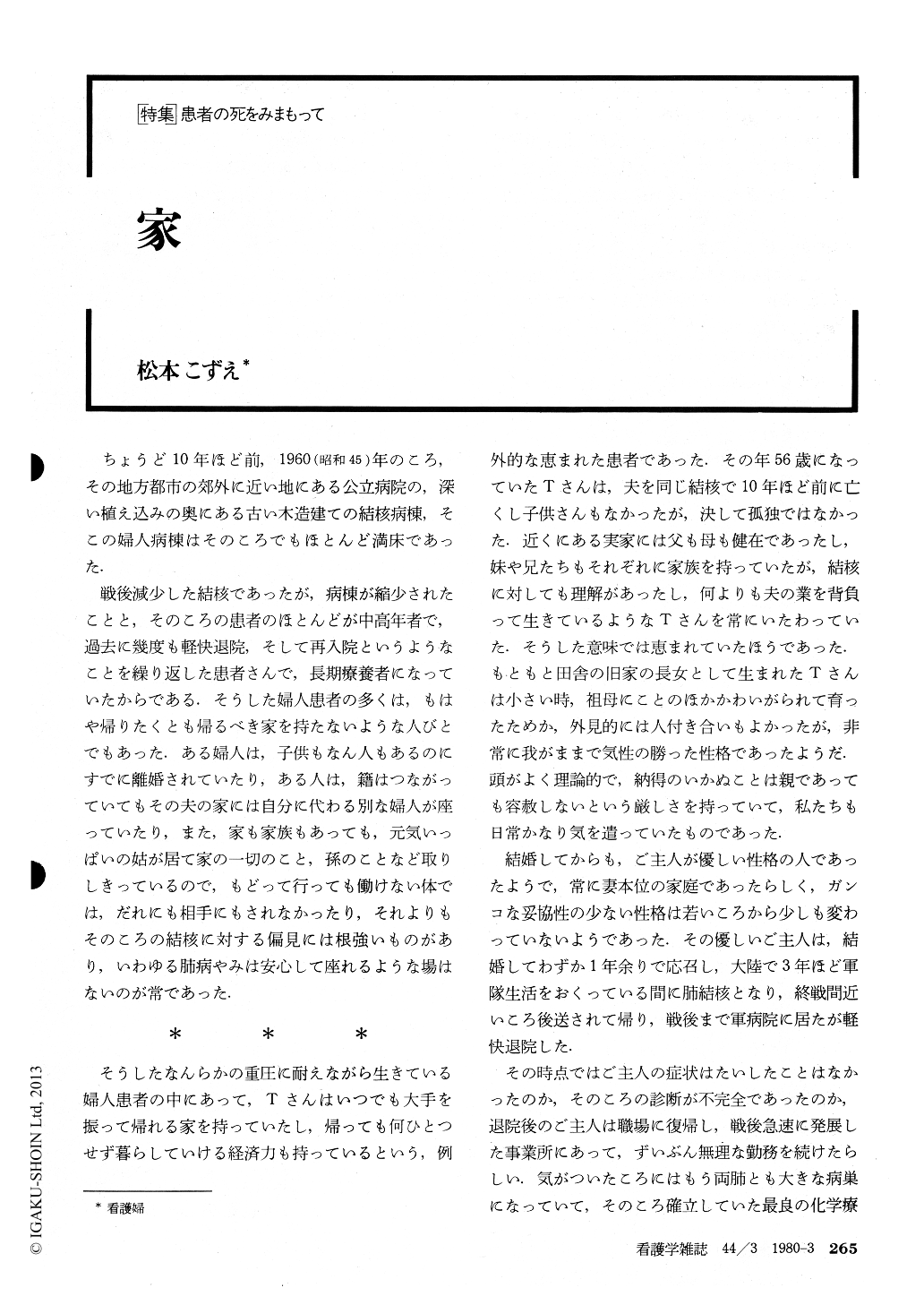
Copyright © 1980, Igaku-Shoin Ltd. All rights reserved.


