今月の臨床 経腟超音波を使いこなす
産科での活用
10.妊娠初期における胎児形態異常の診断
鈴木 久也
1
,
岡村 州博
1
1東北大学医学部産婦人科
pp.466-472
発行日 1998年4月10日
Published Date 1998/4/10
DOI https://doi.org/10.11477/mf.1409903236
- 有料閲覧
- 文献概要
- 1ページ目
急速に普及している経腟超音波診断法により,ある種の形態異常は,妊娠第1三半期においても診断可能となった(表1).形態異常のなかでも致死的な異常については,妊娠早期に診断するほうが望ましいが,妊娠中,あるいは出生後に治療可能な異常であっても,診断された時期が妊娠初期であった場合,両親の考え方によっては人工妊娠中絶の対象となってしまう可能性がある.さらには,妊娠初期の胎児にとっては生理的な所見であるものを異常であると判断し,その旨を告知することで,妊婦やその家族に余計な不安を与えてしまう場合がある.妊娠初期の胎児形態異常の観察においては,解剖学的な知識のみならず発生学の知識が要求される1).
例えば,妊娠初期の頭部嚢胞像を水頭症や全前脳胞症と診断したり(図1),生理的臍帯ヘルニアを腹壁形成異常と思い込んだりしないなどの注意が必要である(図2).経腟エコーで観察した妊娠初期発生段階を示す(図3).一方,胎児形態異常のなかにはさらに妊娠週数が経過しないと診断が困難なものもある.Pretoriusら2)は妊娠24週までに異常像を描出することが困難な胎児形態異常の例として表2のような疾患を挙げている.例えば,多くの消化管閉鎖では胎児の機能的な羊水嚥下が始まらないと口側腸管の拡張が生じないし,閉塞性水頭症も当初からは脳室拡大がはっきりしない場合が多い.
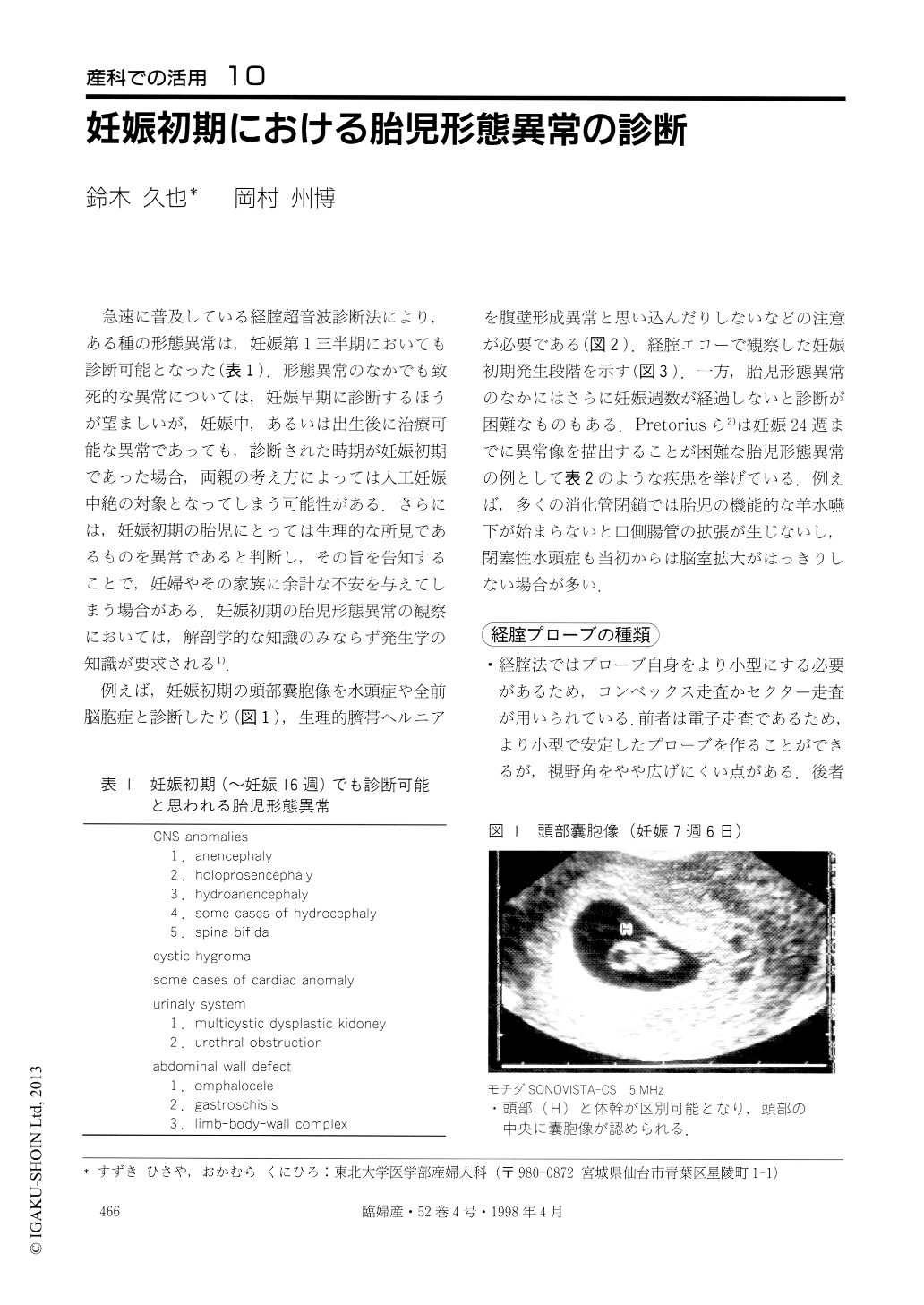
Copyright © 1998, Igaku-Shoin Ltd. All rights reserved.


