検査法
骨・軟骨の病理組織学的観察法(III)—病変の組織表現(2)
三友 善夫
1
Yoshio MITOMO
1
1東京医科歯科大学病理学教室
pp.520-533
発行日 1970年7月25日
Published Date 1970/7/25
DOI https://doi.org/10.11477/mf.1408904425
- 有料閲覧
- 文献概要
- 1ページ目
I.骨・軟骨の形成異常と生検
病理組織検査で取り扱われる整形外科領域の材料のうち,腫瘍や腫瘍類似の病変をのぞくと炎症性病変と血管障害性病変はともかくとして内分泌疾患や代謝異常に原因する全身性または単発性に発現する形成異常に対応する先天性発育異常による骨・軟骨疾患の形態像の認識把握にはしばしば困惑させられる.また遺伝的検索によつて染色体の組成や構造の異常が明らかな一群の疾患にあつて,これらの骨・軟骨疾患の細別や発現の程度などを知るために試みられる生検にもおのずから制限があり,時にはまつたく無能に等しい場合も少なくない.とりわけ軽症の先天性形成異常を示す骨・軟骨の病変部位は変形や骨折の発現ののちにはじめて生検が行なわれることが多いために繰り返される骨折のもつ多彩な形態像が原疾患を被覆して生検像は複雑となる.たとえば骨形成不全症osteogenesis imperfectaの定型例や重症例は死産児や生後1〜2年の乳児が大部分で,解剖材料にはなるが生検の対象となる機会は少ない.しかしながらまれではあるがこの疾患の小児思春期型や成人型の病変部位の小切片やこの病変に随伴しやすい骨折部分の断片的な材料から適確に診断し,骨折の原因となつている骨形成不全症を探り出すことが常に必ず可能であるとは限らず,診断し得たとしてもその病変の進展の程度や強さまで把握し,予後まで推定することは容易ではない.そのうえ遺伝的要因をもつ先天性骨・軟骨疾患をもつ個体は比較的感染症を伴いやすく,骨折に加えて炎症性変化や退行性変化を合併しがちで,原疾患の診断はますます困難となる.
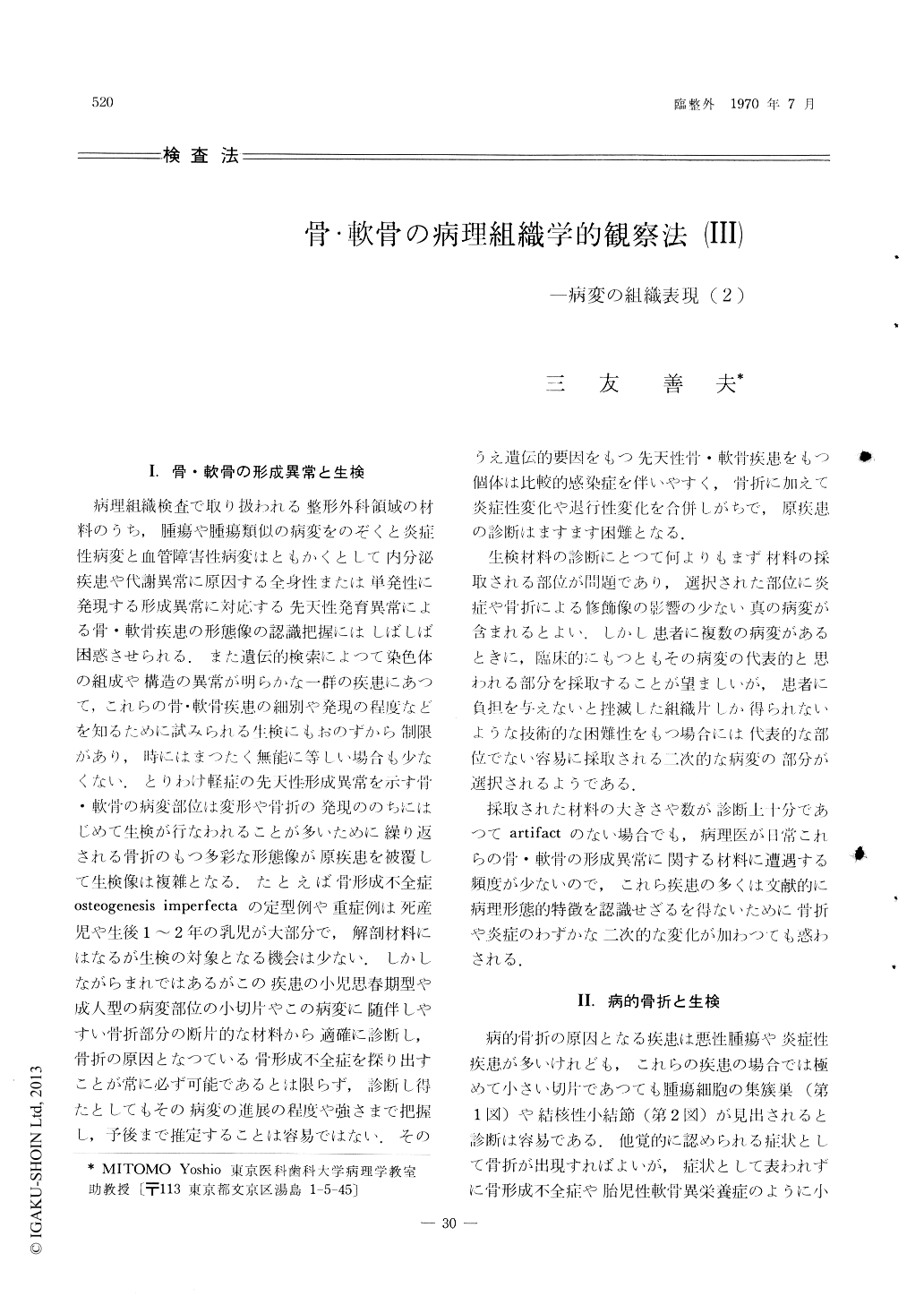
Copyright © 1970, Igaku-Shoin Ltd. All rights reserved.


