- 有料閲覧
- 文献概要
- 1ページ目
- 参考文献
はじめに
この度,頚椎椎管拡大術(服部法)の開発の経緯について記載することを依頼された.歴史的な意義があるとはいえ,すでに時代は変遷しており,昔話をすることを躊躇していた.しかし,恩師服部奨先生の偉大なご業績の1つであり,それを直接に体験した私が恩師に対する深い敬意を表するためにも,当時の思い出を記しておくことも許されるであろうと判断した.
頚椎の手術的治療は,後方進入法による頚椎椎弓切除術や椎弓部分切除術から始まっていた.しかし,手術器具が未発達の時代は手術成績が優れなかったので,手術適応は厳選されていた.1960年代に前方法が導入され,術後成績が飛躍的に向上し,頚椎前方法が主流の時代になった.この頃には,全身麻酔が定着し,手術器具が精巧に改良されてきた.前方固定の術後期間が長くなるにつれ,固定隣接椎間の障害が課題となり,後方進入法が再び評価されてきた.桐田良人先生の広汎同時性椎弓切除術は後方法の導入を加速させ,後方法は前方法とほぼ同様の術後成績が得られ,両術式は症例によって使い分けて用いられるようになった.後方法は,特に多椎間罹患の頚髄症や頚髄腫瘍などの広範囲の除圧を要する場合にはよい適応である.しかし,後方法は頚椎の後方要素を摘出し,頚椎の支持性の減弱を来たすことは否めず,特に,若い年代では術後に頚椎変形がかなりの頻度で出現していた.
そこで,頚髄の十分な除圧と頚椎の後方要素の減弱を可及的に軽減するために,頚椎の後方要素の構築的再建を行って,従来の後方法の欠点を補うことを目的に,服部先生は1971年に「頚椎椎管拡大術」を開発して報告された.その後,平林洌先生・黒川髙秀先生などによって各種のlaminoplastyが報告されており,現在では,種々の方法が適宜実施されている.ただ,頚髄の後方除圧とともに頚椎の後方要素を可及的に温存するという発想は服部先生が最初であり,当時は画期的な考え方で,その開発が契機となって各種の後方法が普及した.
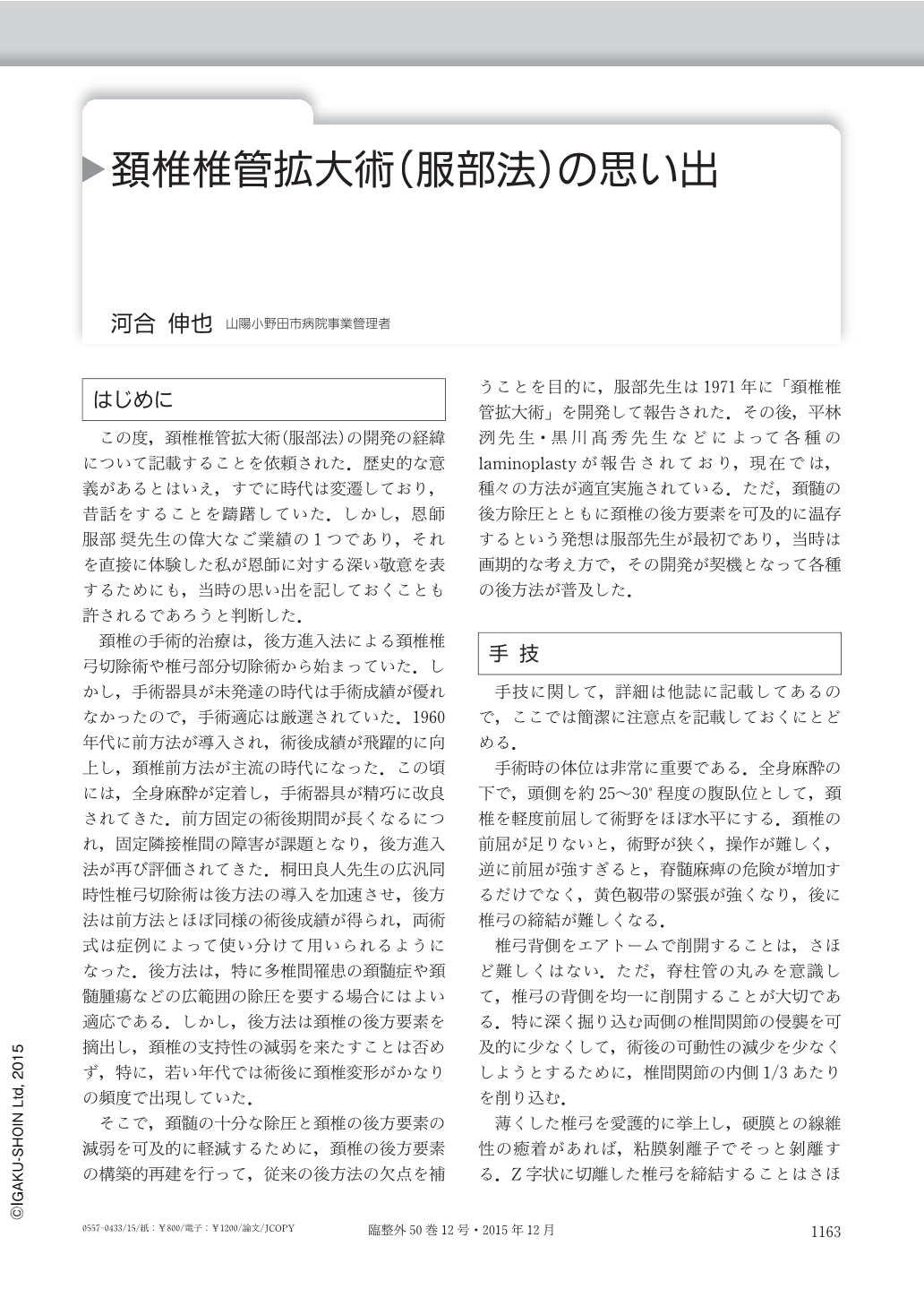
Copyright © 2015, Igaku-Shoin Ltd. All rights reserved.


