- 有料閲覧
- 文献概要
- 1ページ目
- 参考文献
はじめに
精神科医の中井久夫(1934〜2022)は、統合失調症やPTSDの治療と研究、風景構成法の開発、阪神・淡路大震災に際しての積極的なケア活動、神戸市須磨区の連続児童殺傷事件における精神鑑定、医学書の邦訳、更にはエッセイや評論といった一般読者に向けた執筆活動など、多岐にわたる仕事をしました。しかもその分野は医療に留まらず、「継ぎ穂理論」や「執筆過程の心理」のような言語論、ヴァレリー、カヴァフィス、リッツォスといった詩人の翻訳、『治療文化論』や『西欧精神医学背景史』などの歴史や文明史など、文学や人文学にまで及びます。あまりにも広汎な仕事ぶりに、本当に一人の人間なのか?と疑いたくなるほど(恥を忍んで告白すれば、まだ中井をよく知らなかった頃は、精神科医と翻訳家に中井久夫という同姓同名の人物がいるんだなと本気で思っておりました)。
その仕事の中心にあるのはもちろん医療です。しかし先述のように文学等の仕事も膨大かつ重要であるため、そうした側面から中井をきちんと論じないことの喪失は計り知れません。かく言う私は中井について、小林秀雄や加藤周一といった批評家(文学者)の一人として親しんできました。
そこで、主に文学を仕事としている立場から、中井の遺した言葉を読むのが、この連載の趣旨です。主眼となるのは、中井の文体や言語観、文章観を通して、何かを論じること(批評や評論)の在り方を考え直すことにあります。そのために、中井が何を語ったかはもちろん、「どう語ったか」にも注意深く目を向けます。難解な医学や文学を語っていたとしても、中井の言葉は平明かつ大らかで、読者と同じ目線に立ち、いかに伝えるか、いかに開かれた言葉を紡ぐかに細やかな心配りがなされていました。ですから、その語り方にも、中井らしさが宿っていることは間違いありません。
批評というフィールドに話を広げますと、ここ数年に至ってようやく、ケアやフェミニズムのような新しい批評の在り方が生まれています。しかし長らく批評の文体と言えば、マッチョで晦渋なものが幅を利かせていました。そんな中で中井の言葉は、鋭いながらも、平易で優しく、温かみと配慮に溢れています。したがって、いま中井の文章を読むことは、次の批評を考えるヒントになるはずです。
念の為に補足しておくと、弱者や病気に対する中井の考えを論じることも、重要な目的です。というのも、医師としての中井と文学者としての中井は同一人物であり、総体として捉えなければ大切なものを見落としてしまいますし、それこそが中井独自の批評スタイルの核になっているからです。
以上のような思いから、人間・中井久夫を通して、特に文学や批評の在り方を問い直していきたいと思います。
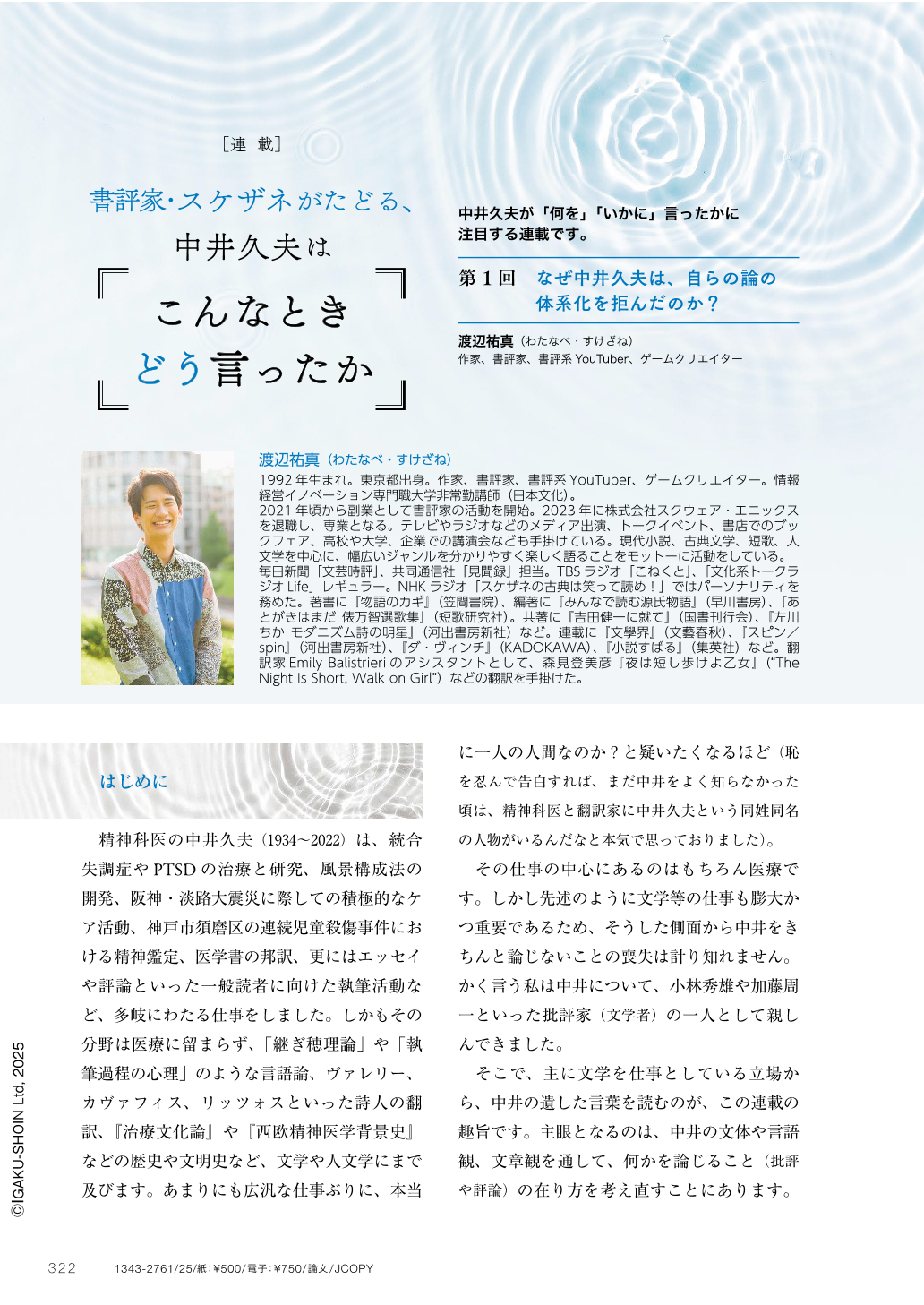
Copyright © 2025, Igaku-Shoin Ltd. All rights reserved.


