- 有料閲覧
- 文献概要
- 1ページ目
- 参考文献
はじめに
インクルーシブ教育が推進されるとともに,2012年(平成24年)にその実現のための一丁目一番地として「保育所等訪問支援事業」が設定された1).障害のある子どもの集団参加を後方支援する役割として,専門職が保育所や学校に参加できるようになった非常に画期的な事業である.特に,児童発達支援施設に所属する子どもたちが就学するときに,本人やご家族の不安に寄り添い,その後の学校生活が円滑に過ごせるように施設職員が直接学校現場で教員に引き継ぎができるこの制度の開始は,地域での活動参加支援を行うわれわれ作業療法士にとって福音ともいえるものであった.2012年の事業開始当初より,個別支援計画実現のための地域連携の中で,作業療法士が直接保育所や学校に訪問できる制度は重要であるとの認識はあったが,実際にインクルーシブ教育を推進するには,さまざまな障壁があることも現実である2).
2012年当時,筆者も含め多くの作業療法士は病院や入所施設で働いていた.医療機関から訪問することは,院内業務との関係や経済的理由からなかなか実施困難であった.また,保育所や学校における受け入れ準備もほとんどなく,制度の説明から行う必要があった.その後,地域の児童発達支援施設・放課後等デイサービスでの日常的な連携手段として徐々に認知されるに至り,現在,当事業所では市内対象に12名の訪問支援員が120名〔2025年(令和7年)4月現在〕を対象に支援を実施している(図).訪問先は,保育所,幼稚園,小学校,中学校,高校と多岐にわたり,就学前から利用していた子どもの80%近くが地域小学校に就学している.保育所との信頼関係を構築し,地域ケア会議を重ねて地域就学に至った事例を振り返り,就学に向けた保育所での作業療法士の支援について考えたい.
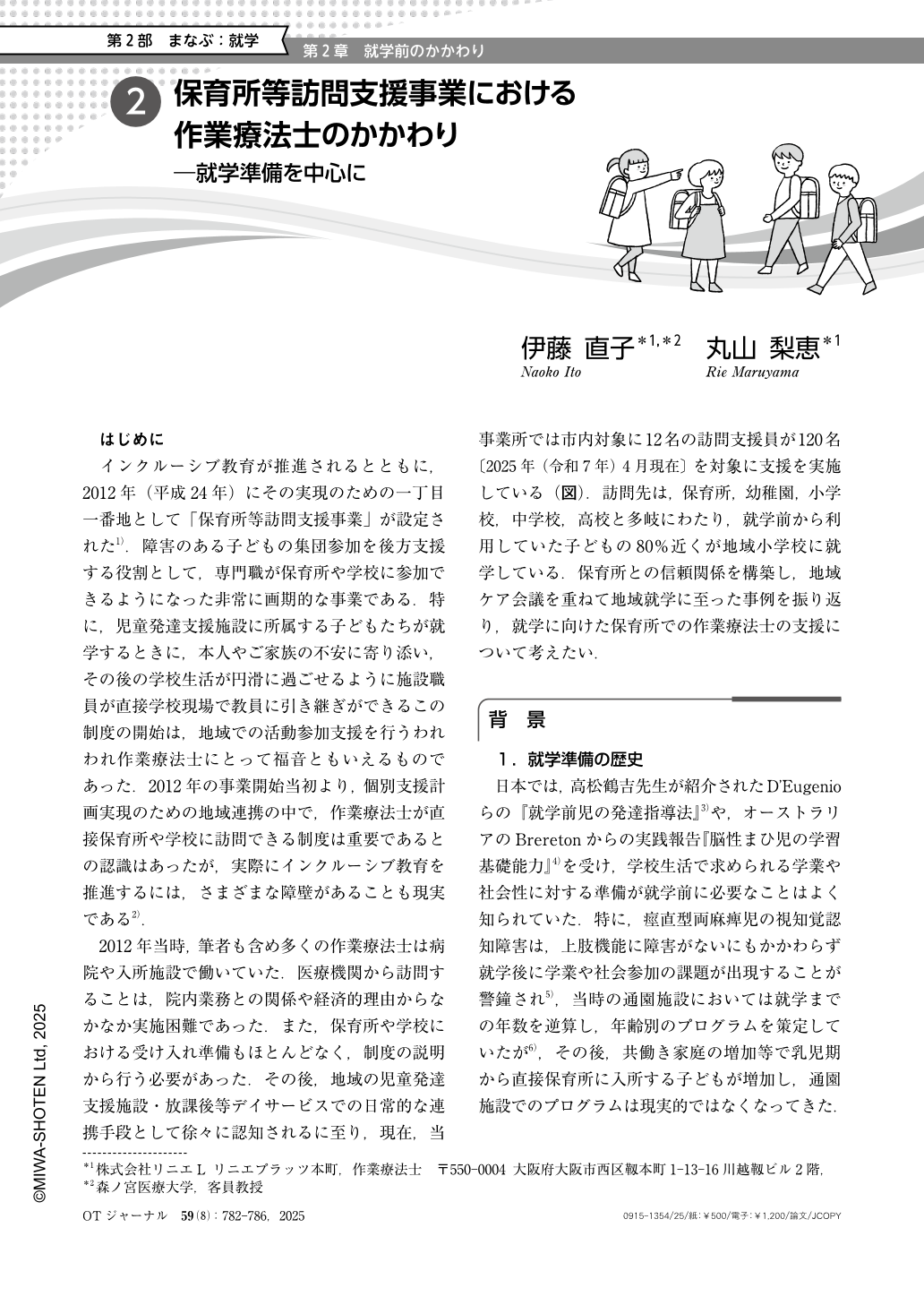
Copyright © 2025, MIWA-SHOTEN Ltd., All rights reserved.


