連載 デジタルアウトリーチの進化が切り拓く新たな可能性・第2回
学術系VTuberによるデジタルアウトリーチの実践とその可能性
Rue
Rue
キーワード:
デジタルアウトリーチ
,
科学コミュニケーション
,
VTuber
,
相互コミュニケーション
,
推し活
Keyword:
デジタルアウトリーチ
,
科学コミュニケーション
,
VTuber
,
相互コミュニケーション
,
推し活
pp.943-947
発行日 2025年9月10日
Published Date 2025/9/10
DOI https://doi.org/10.11477/mf.038698220530090943
- 有料閲覧
- 文献概要
- 1ページ目
- 参考文献
はじめに
近年,科学技術に対する一般社会の関心低下が問題視されており,その対策として,研究者や研究機関が研究成果を社会に向けて発信するアウトリーチ活動の重要性が高まっている.
最近では,講演会やワークショップといった従来型のアウトリーチに加え,YouTubeやsocial networking service(SNS)などを活用したデジタルアウトリーチも広まりつつある.そのなかでも,バーチャルなキャラクターモデルを通じて科学的な情報を発信する「学術系VTuber」が,新たなアウトリーチ手法として注目されている.専門性をもつ個人が,視聴者に親しみやすい形で科学を届けるこの手法は,従来の手法では接触が難しかった層への新たな接点として注目されている.
ここでは,学術系VTuberとして5年以上活動し,日本神経科学学会の広報職「ニューロナビゲータ」や研究者との対談イベントを企画してきた筆者の経験・知見をもとに,学術系VTuberによるアウトリーチの可能性を検討し,その特徴・実践例・課題・今後の展望について考察する.
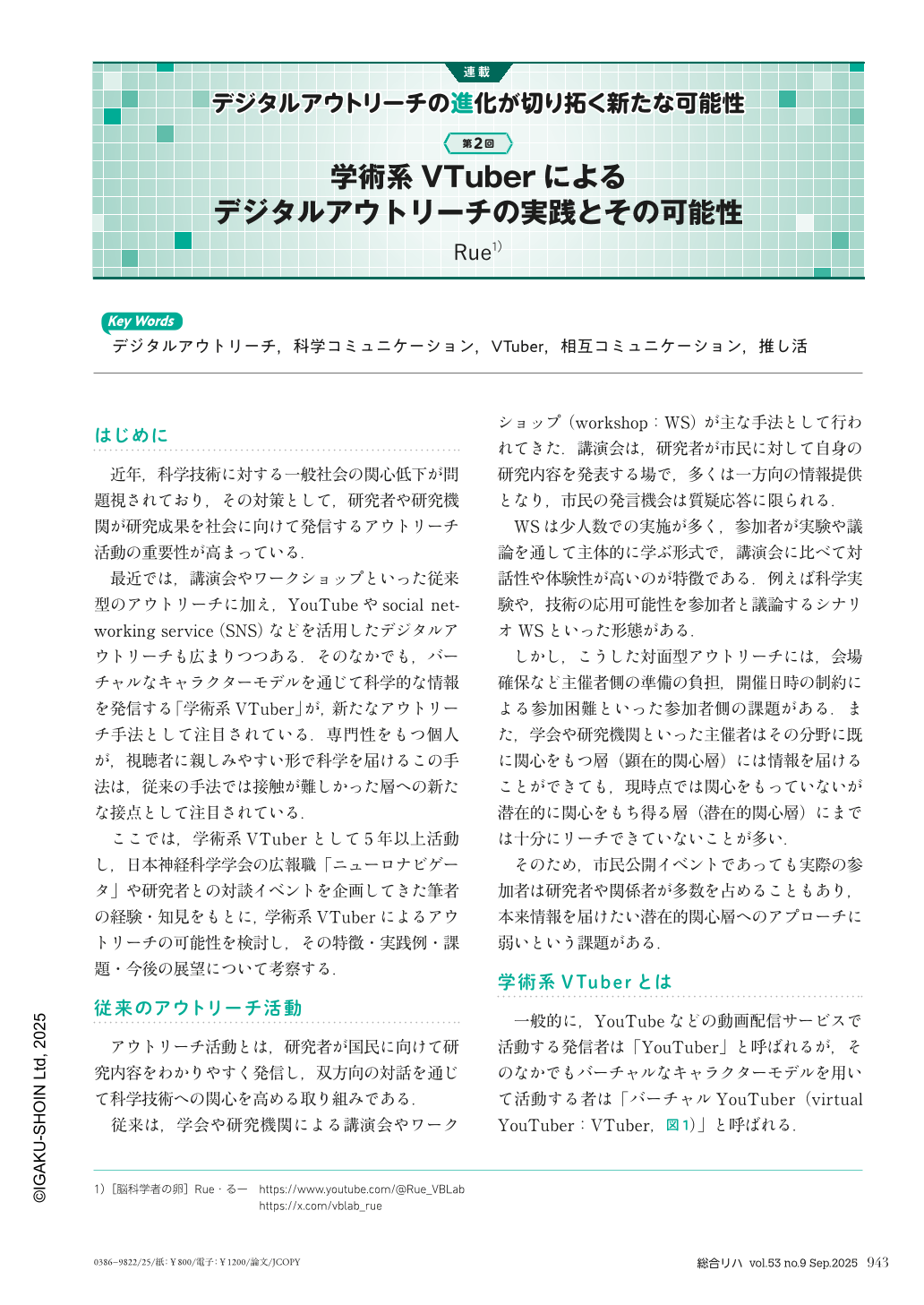
Copyright © 2025, Igaku-Shoin Ltd. All rights reserved.


