- フリーアクセス
- 文献概要
- 1ページ目
日本の出生数は年々減少し,2024年には68万6061人となり過去最低でしたが,2025年にはさらに減少することが予想されています.待ったなしの少子化対策として不妊治療への期待は高まるばかりです.これまで不妊夫婦の48%(約半数)に男性側因子が存在することがよく知られていますが,この統計は1993年,WHOの報告に基づくものですから,現在ではさらに男性不妊症の割合が増えていることも推測されています.2021年11月に日本生殖医学会編集による『生殖医療ガイドライン』が日本で初めて出版されました.それを受けて2022年4月より不妊治療が保険適用となりました.この劇的な変化により,泌尿器科を受診する男性不妊症患者が増加しています.そこで,さらに男性不妊症に特化した『男性不妊症診療ガイドライン』が2024年2月に日本泌尿器科学会編集(日本生殖医学会後援)にて発刊されています.現在,一般泌尿器科においても標準的な診療が行える環境が整いつつあるところかと思われます.
ただし,『男性不妊症診療ガイドライン』が発刊されたからといって,すべてが解決,理解できるほど男性不妊症に対する診療は簡単ではありません.実際,臨床の現場では絶えずどう対応すべきか悩んでしまう臨床的問題に直面します.精液所見が不良だった場合に泌尿器科でなんらかの治療を試みるべきなのか,あるいはすぐに婦人科と連携して人工授精,体外受精に進むべきなのかなど,それぞれのご夫婦のご希望も交えて判断していく必要があります.今回,現場で遭遇する素朴な疑問を集めてみました.それらの疑問に対して実際にどのように考えたらいいのかをそれぞれのエキスパートの先生方に詳しく解説いただいています.本特集が男性不妊症に対する診療の一助になることを願っております.
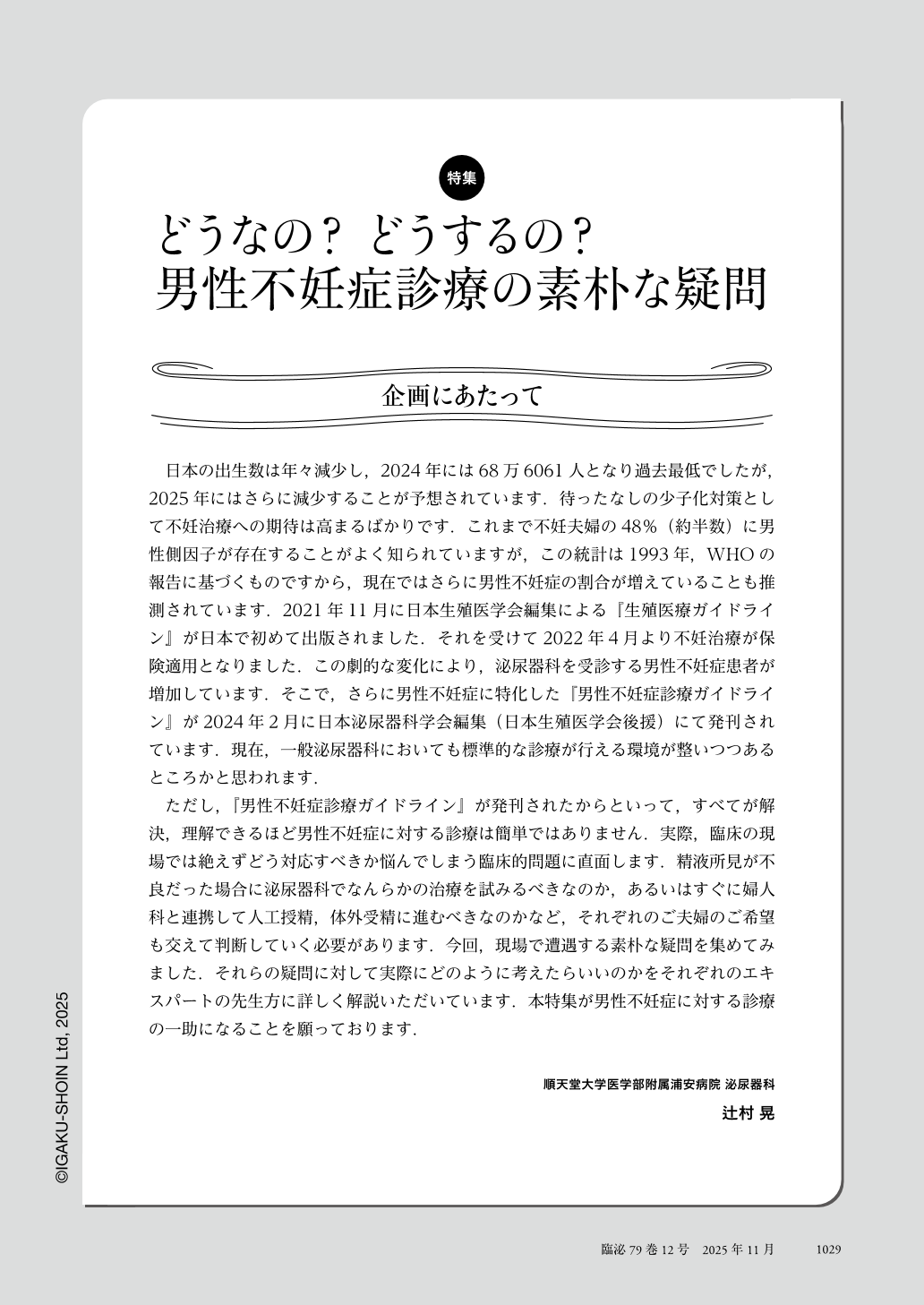
Copyright © 2025, Igaku-Shoin Ltd. All rights reserved.


