連載 新型コロナウイルス感染症のパンデミックをめぐる資料、記録、記憶の保全と継承—「何を、誰が、どう残すか」を考える・8
COVID-19関連資料のアーカイビングをめぐる研究倫理の諸課題
井上 弘樹
1
1東京医科大学医学部医学科人間学教室
pp.735-738
発行日 2025年8月15日
Published Date 2025/8/15
DOI https://doi.org/10.11477/mf.036851870890080735
- 有料閲覧
- 文献概要
- 1ページ目
- 参考文献
研究倫理をめぐる対話
これまでの本連載を振り返るとCOVID-19に関連する資料には、行政機関や学校などが作成した文書、街中のビラ、新聞記事、統計データ、芸術作品、日記、写真、映像、モノ(マスクなど)、web上の情報、インタビュー記録(語り、記憶)などがある。アンケートやフェイク(とされた)情報、病院で管理される試料やカルテも資料となる。では、COVID-19関連資料を調査・収集し、整理・保存して、利用を伴いながら継承するという一連の研究(以下、アーカイビング)は、「人を対象とする研究」としてどのような研究倫理の課題があるだろうか。
本誌読者は人を対象とする研究倫理と聞くと、ヘルシンキ宣言や「人を対象とする生命科学・医学系研究に関する倫理指針」(生命・医学系指針)などを思い浮かべるだろう。いわゆる人文社会科学系の研究も生命・医学系指針の適用対象になり得る1。しかし、質的研究を行う社会学や看護学などからは、研究倫理の重要性は認めた上で、そうした適用対象の判断や倫理審査がしゃくし定規で、多様な研究の展開を阻害しかねないと繰り返し指摘されてきた1)。COVID-19関連資料のアーカイビングでも同様に研究倫理をめぐるこうした隔たりは生じ得る。
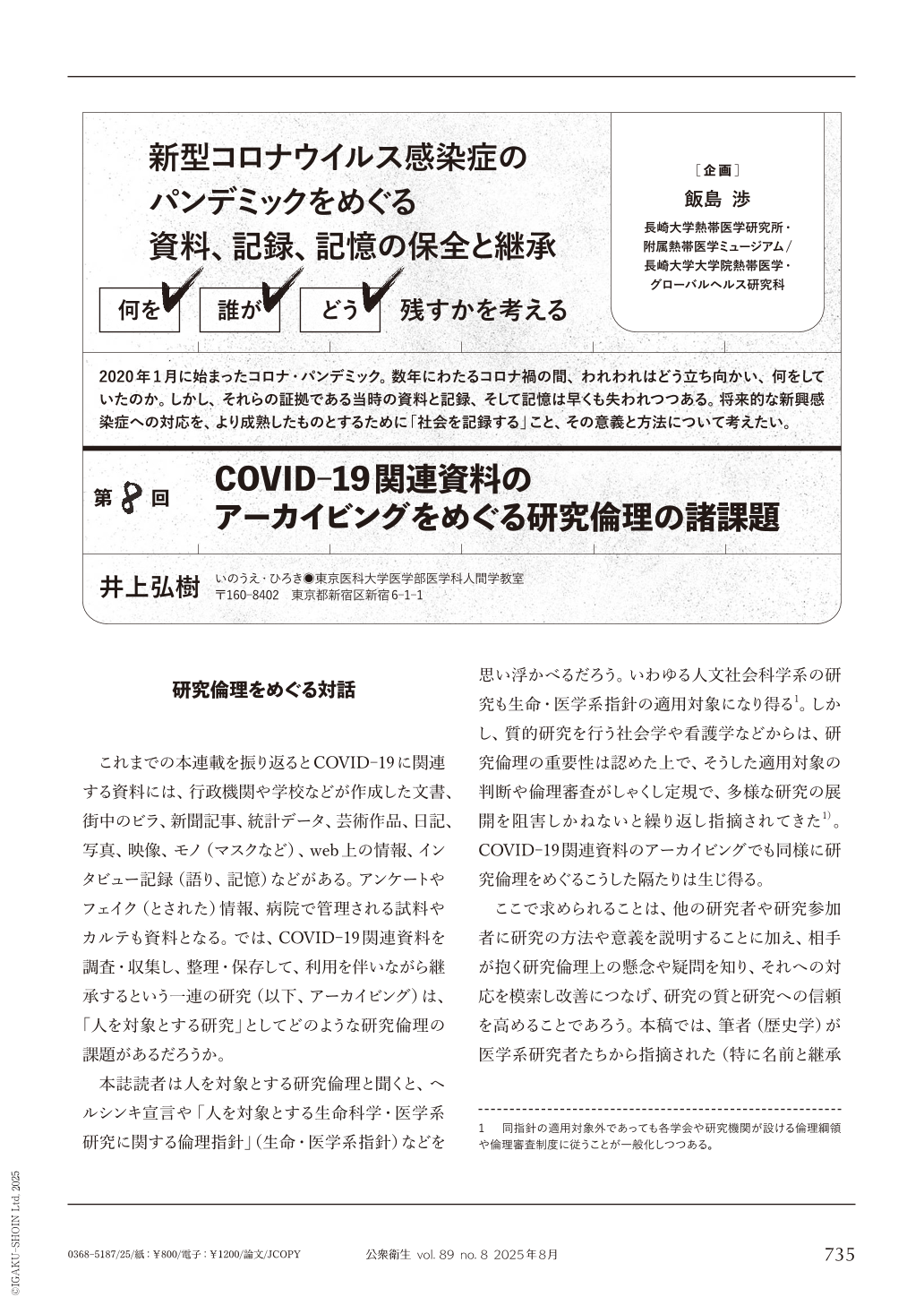
Copyright © 2025, Igaku-Shoin Ltd. All rights reserved.


