- 有料閲覧
- 文献概要
- 1ページ目
- 参考文献
はじめに—小さな困難解決の第一歩となる地域の身近な場所
かつて精神病院に勤め,現在地方都市でNPO法人を運営する作業療法士の男性に,NPO法人を立ち上げて精神障害者の地域生活を支援する理由を尋ねた。彼は,「患者が精神病院に来る前に(患者の状態を)知っていれば何とかなったのに」と回答をした。その主旨はこうである。困難が複雑化してこんがらがってから病院に来ても対処することが難しくなるので,困難が軽微な段階で複雑化する前に対処できていれば,病院に来ることなく自宅で生活できていたはずである。
仕事や子育て,病気など,日常的に生活で何らかの困難を抱えることはある。例えば定年退職した男性に対して「地域デビュー」という言葉があるが,定年後の男性が,住んでいる地域でどう過ごすのかが課題であることを意味する。近所に男性が活躍できる場所があることや居場所が見つかれば,地域デビューがうまくいくが,うまくいかず孤立してしまい健康を害してしまう場合もある。
このような困難を解決するために情報や知識,経験,方法を持ち合わせている人は解決できるだろう。一方でそれらを持ち合わせていない人は解決することは難しく,最初のつまずきがより大きくなっていき困難が複雑化していく。困難を解決する方法で特に重要なのは,住んでいる地域の身近な場所で相談できることである。
古い調査研究だが,筆者は住民ボランティアによる「ひがしまち街角広場」(大阪府豊中市)というコミュニティカフェで調査を行った。インタビューした主(あるじ)の言葉を紹介する。「いわゆる喫茶店とかじゃなくていろんなものの情報の集まる場所ですし,ここから発信もしています。いろんな人の交流場所,交差点ですね。すべての交差点になっていますよね。ここに来ればどうにかなる」。そして,生活のあらゆることがここに来れば,「何でも聞いたら誰かその場にいる人たちが山ほど教えてあげられる。そこまで聞いてへんっていうとこまで教えてくれる」と述べている(松原,鈴木,2003)。いわゆる駆け込み寺の役割である。また「ヨリドコ大正るつぼん」という施設では,毎月2回,「要援護者が抱える将来や,人生や社会についての漠然とした不安。そんな深刻になる前の芽の状態で困りごとを拾いあげ,支援サポートする」取り組みとして「ミナの語り場」を実施し,誰もが自由に参加でき,地域住民や地域の専門職も参加している註。
上記のように,何らかの困難が生じた場合にはできるだけ早く,生活している場の近くで解決できる取り組みが有効である。
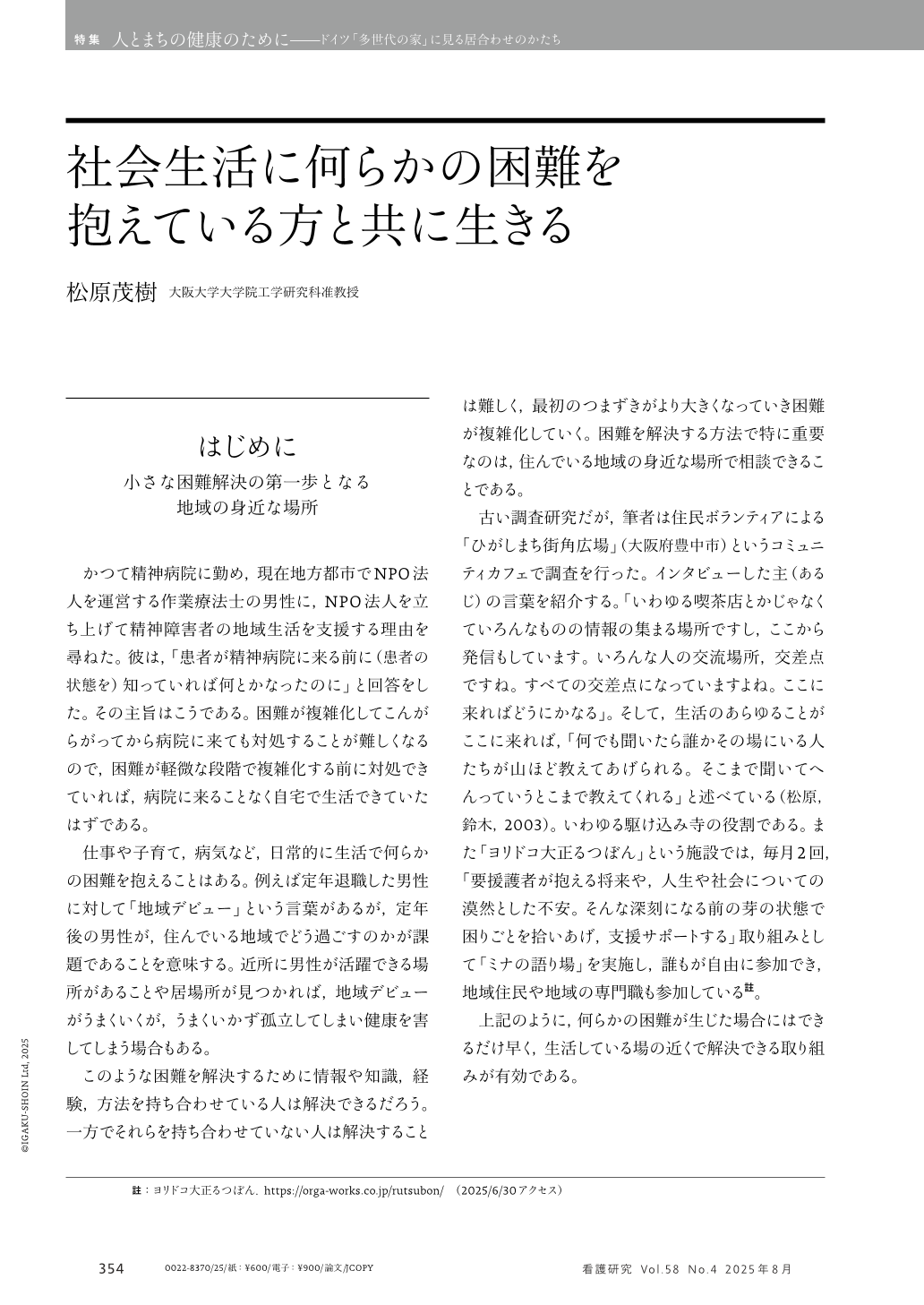
Copyright © 2025, Igaku-Shoin Ltd. All rights reserved.


