- 有料閲覧
- 文献概要
- 1ページ目
- 参考文献
I はじめに
村瀬嘉代子は,生前,数多くの著書を発表したが,なかでも『柔らかなこころ,静かな想い―心理臨床を支えるもの』(村瀬,2000)は彼女のお気に入りであった。本書は,1998年に亡くなった夫,孝雄に対するあふれんばかりの追慕の情を綴った一編を含む自伝的エッセイ集であり,彼女の良き理解者であった中井久夫が挿絵を手がけた珠玉の一冊である。後に村瀬は心理職の国家資格化に取り組むようになった際に,初対面の国会議員や官僚に名刺代わりに心理学の専門書ではない本書を手渡していたという。心理学の専門家ではない相手に自分がどのような人間かを知ってもらうのには,同書を介するのが最も良い方法であると考えたのである。それは,村瀬が心理臨床の現場においても初めて向き合う被援助者にまずは自分の専門性よりも人間性を示して見せたことに通じよう。
それにしても,村瀬嘉代子が静かに回想するエピソードの数々は,なんとひそやかなきらめきを放っているのだろう。彼女は,幼い頃から恐ろしく研ぎ澄まされた感性の持ち主であった。わずかに6歳にして,日米開戦直後の日本がこの戦争に勝つことはないと見抜き,また「人は直接加害的行為をしなくても,存在自体が罪であることがある,罪があっても生かされている」と心を痛めるほど早熟な子どもであったという(村瀬,2000;村瀬ほか,2024)。後に,そのことを知った土居健郎は,「幼くして子どもの心を失った人だね」と,つい村瀬本人に感想をもらしている(村瀬,2024)。村瀬のような「子どもらしくない子ども」は,思春期青年期に至るとさまざまなクライシスに陥るであろうと懸念される。その非凡さゆえに周囲に容易に溶け込めずに苦しむこともあったに違いない。しかし,幸運なことに村瀬は厳しくも慈愛深く育てた両親や伴侶となる孝雄をはじめ,有名無名を問わず,さまざまな人々に支えられながら困難な時代を生き抜くことができた。どんな時もどんな人をも惹きつける稀有な才能もあったのである。かくも村瀬は,おのれのBildungsroman(成長物語)を厳かに開示して見せたのであった。
実は,筆者は最晩年の村瀬に『臨床心理学』誌の特集企画で幾度かインタビューする機会があったが,そんな時も彼女は自分の幼い頃の疎開先での思い出や,家裁調査官時代のプライベートな体験を回顧した(村瀬,2024;村瀬ほか,2024)。7,80年近く前の遠い日の出来事も昨日のことのように生々と話す彼女の語り口に惹き込まれた筆者は,思わず「まるで朝の連続テレビ小説のヒロインじゃないですか!」と叫んだものである。それほど,村瀬の生きた道のりはあまたの心理臨床家のなかでも際立っていた。それが多くの識者をして「村瀬だからできる,村瀬にしかできない」と言わしめた臨床家として特異な器量を支えていたことは明らかであろう。
それにしても晩年の村瀬は,どうしてあのように自分の希少な体験をおよそ真似しようがない私たちに語りたかったのだろうか。本来,極めて思慮深い人であっただけに,いささか訝しく思う。本稿は,そのような筆者の疑問が執筆の動機となっている。
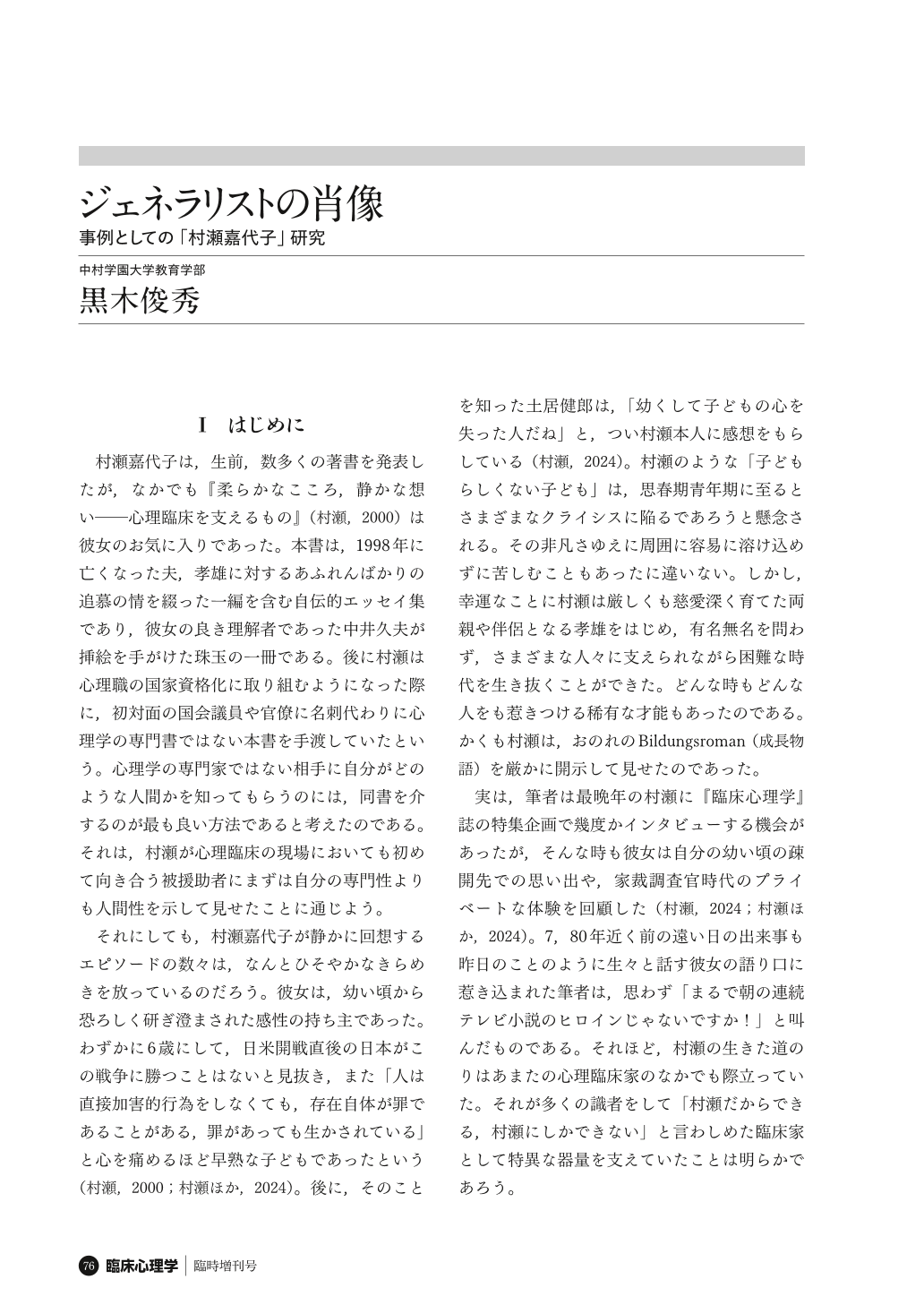
Copyright© 2025 Kongo Shuppan All rights reserved.


