- 有料閲覧
- 文献概要
- 1ページ目
- 参考文献
大学院の心理アセスメントの授業の内容は盛りだくさんである。心理測定法の基礎理論に続いて,観察法,面接,検査などといった方法の特徴についてふれたら,妥当性と信頼性の概念の説明が続く。そのあとは,次々に心理検査が紹介されていく。いくつかの検査については手に取ってそれらを実施して手続きを学ぶこともできるが,その数は限られている。一連のアセスメントの流れ―臨床面接で問題状況について把握し,仮説を立て,それに基づいてテストバッテリーを組み,それを実施し,結果を解釈して,その他のデータと統合し,心理レポートにまとめ,本人にフィードバックもする―を経験する機会はさらに少ない。そのプロセスを通して,アセスメントのスーパービジョンを受けるとなるとなおのことであろう。たしかに,さまざまな検査について知れば,選択肢は広がり,アセスメント状況に合った検査を選びやすくなる。また,特定の心理検査の手続きを一通り覚えることも,当然ながら必須である。しかし,現実世界のアセスメントの複雑さを学ぶためには,それ以上の学びと訓練が必要となってくる。というのも,実際の現場で必要とされるのは,単に特定の心理検査を選んでそれらを正しく施行して結果を出すだけではないからだ。
臨床心理アセスメントについて効果的に学ぶためには,ケースに基づいた学習が効果的である。特定の現場,そして支援を求める人や関係者が織りなす状況とさまざまな現実的制約のなかで,できるかぎり効率的かつ包括的にデータを集め,分析し,信頼できる結論を提示できるか,そしてそれを本人と関係者が最もうまく活用できるような形で提供できるかがアセスメントの鍵である。だからこそ,ケースを通してこそ最も効果的に学ぶことができるのだ。
本増刊号は,まず基盤となるアセスメントの知識について概説した後,さまざまな臨床現場や状況においてどのようにアセスメントが実践されているのか事例を通して学んでいく。それぞれの状況において,どんな臨床的推論や臨床的判断のもとでアセスメントが実装されるのかを見ていくことで,読者は知識と手続きの学習を超えた心理アセスメントの広がりについて学ぶことができるだろう。
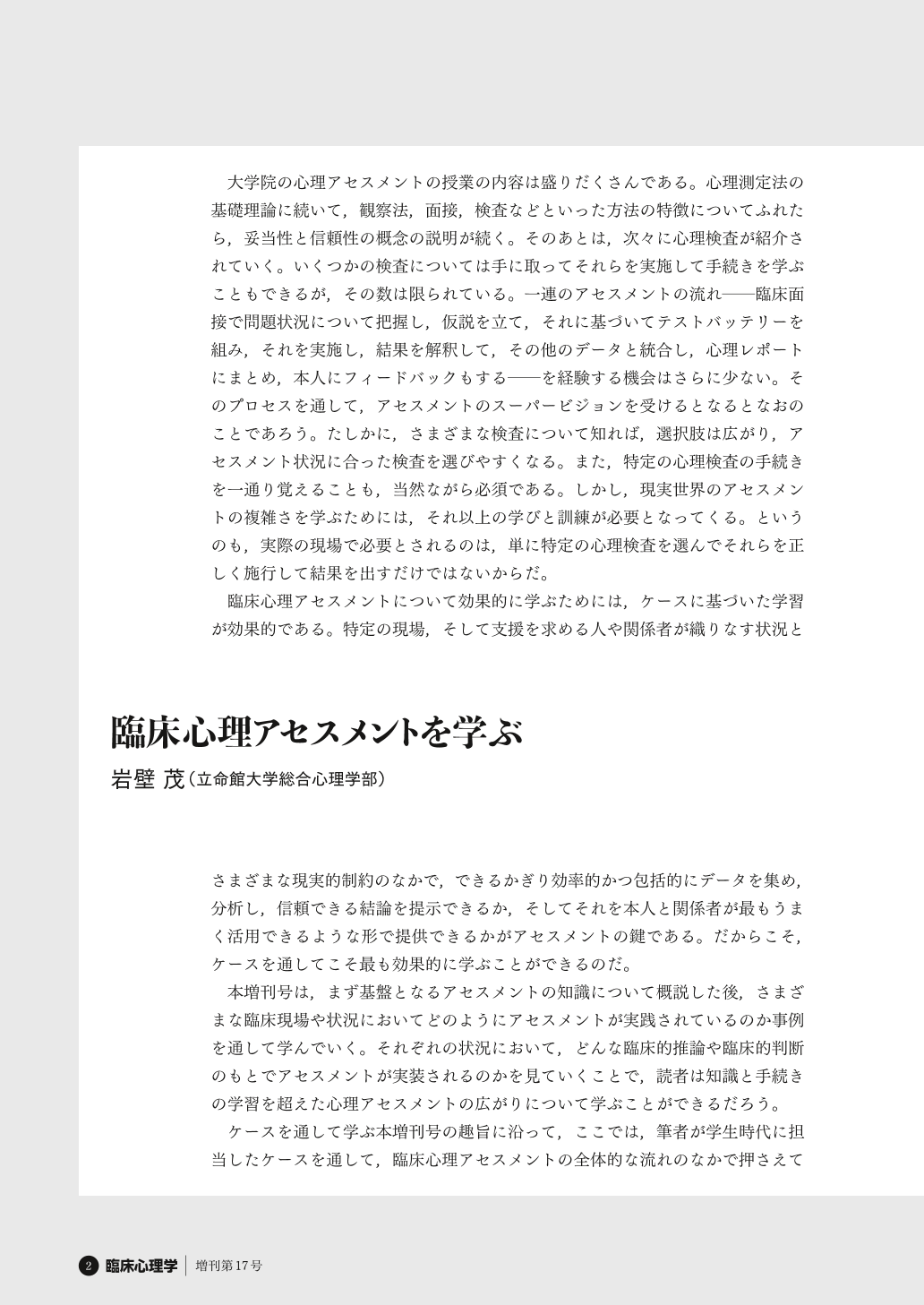
Copyright© 2025 Kongo Shuppan All rights reserved.


