最新版! 摂食嚥下機能評価―スクリーニングから臨床研究まで
18.嚥下CT
稲本 陽子
1
1藤田医科大学保健衛生学部リハビリテーション学科
キーワード:
CT
,
嚥下
,
3次元
,
舌骨
,
喉頭
,
咽頭
,
食道入口部
Keyword:
CT
,
嚥下
,
3次元
,
舌骨
,
喉頭
,
咽頭
,
食道入口部
pp.1266-1271
発行日 2025年11月15日
Published Date 2025/11/15
DOI https://doi.org/10.32118/cr034121266
- 有料閲覧
- 文献概要
- 1ページ目
- 参考文献
背景と目的
1970年代に登場したCTは, 体内の構造を平面で鮮明に描出することを可能にし,医療における画像診断を飛躍的に進歩させた.その後,臨床ニーズと工学技術の進展により,広範囲を短時間でスキャンできる技術や,平面ではなく立体的に構造をとらえる技術が急速に発展した.そして2007年には,16 cm四方の範囲をノンヘリカルスキャン可能な320列面検出器型CTが登場した.この320列CTを嚥下評価に応用したのが「嚥下CT」である 1).
摂食嚥下障害の機器を用いた画像評価としては,嚥下造影検査(VF)と嚥下内視鏡検査(VE)が有用な治療指向的検査法として広く用いられ,嚥下リハビリテーションの発展に大きく貢献してきた.しかしこれらの検査は二次元評価にとどまるため,多くの諸器官が連動して動く嚥下動態をすべて可視化し描出することには限界がある.嚥下CTは,嚥下動態を初めて3次元的,動的,かつ定量的に可視化することを可能とし,嚥下における3次元運動解析を実現した評価法である 2, 3).
検査の意義・目的は,三次元画像により異常所見や機能低下を視覚的に明瞭に描出し,定量評価によって異常の原因となる機能障害をより正確に特定することで,訓練で改善すべき諸器官の運動を明らかにすることである.また再評価により機能改善の程度を定量的に示すことで,選択した訓練効果を検証することも可能になる.
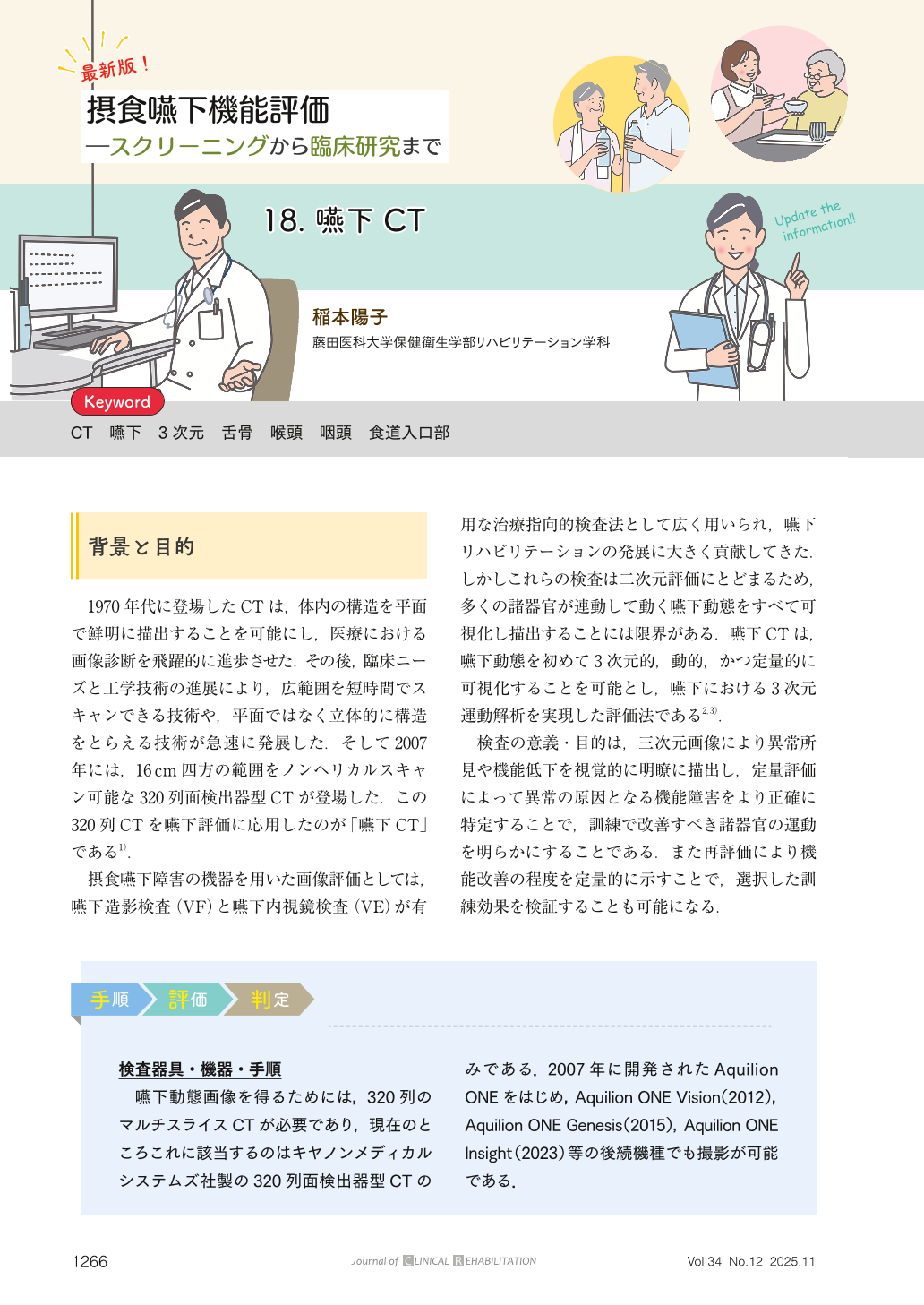
Copyright© 2025 Ishiyaku Pub,Inc. All rights reserved.


