管理栄養士にもできる! オーラルフレイル予防に向けた口腔トレーニングのすすめ〈前編〉
やってみよう! 口腔機能チェックとトレーニング
兼岡 麻子
1
,
荻野 亜希子
1
Asako Kaneoka
1
,
Akiko Ogino
1
1東京大学医学部附属病院 リハビリテーション部 言語聴覚療法部門
pp.148-153
発行日 2025年8月1日
Published Date 2025/8/1
DOI https://doi.org/10.32118/cn147020148
- 有料閲覧
- 文献概要
- 1ページ目
- 参考文献
はじめに
わが国は,65歳以上の人口が全体の21%以上を占める超高齢社会に突入し,健康寿命の延伸が重要な課題となっています1).フレイル(frailty)とは,特定の疾患に起因しない,加齢による虚弱をさす用語で,そのなかでも口腔機能にかかわる虚弱を表すオーラルフレイルは,日本発の概念として注目されています.
オーラルフレイルの概念を図12)に示します.第1レベル「口の健康リテラシーの低下」は,社会的役割の変化などにより自己の口腔健康への興味・関心が薄れ,セルフケアが行き届かなくなることで,健康リスクが高まる段階です.第2レベル「口のささいなトラブル」は,食事や会話にかかわる軽微な口腔機能の低下が起こる段階です.加齢による機能低下に加え,硬い食物を避けるなど食品多様性の低下も相まって,さらに機能低下が進みます.第3レベル「口の機能低下」では,口腔機能低下症などの疾患の段階に至ります.複合的な口腔機能の問題が起きることによる食事摂取量の低下や,活動量の低下による食欲の低下と相まって低栄養に陥り,サルコペニアが進行するという悪循環を招く危険性があります.第4レベル「食べる機能の障がい」に至ると,専門知識を有した医師・歯科医師による対応が必要となります.
オーラルフレイルは健康な状態と要介護状態の間にあり,身体面だけでなく認知面や社会面などの複数の要因が関連している点,また,可逆性がある点3)が特徴です.したがって,病院や施設,在宅訪問など,さまざまな場所での多職種による早期からの観察や声かけが,オーラルフレイル予防やフレイルからの回復につながると考えられます.
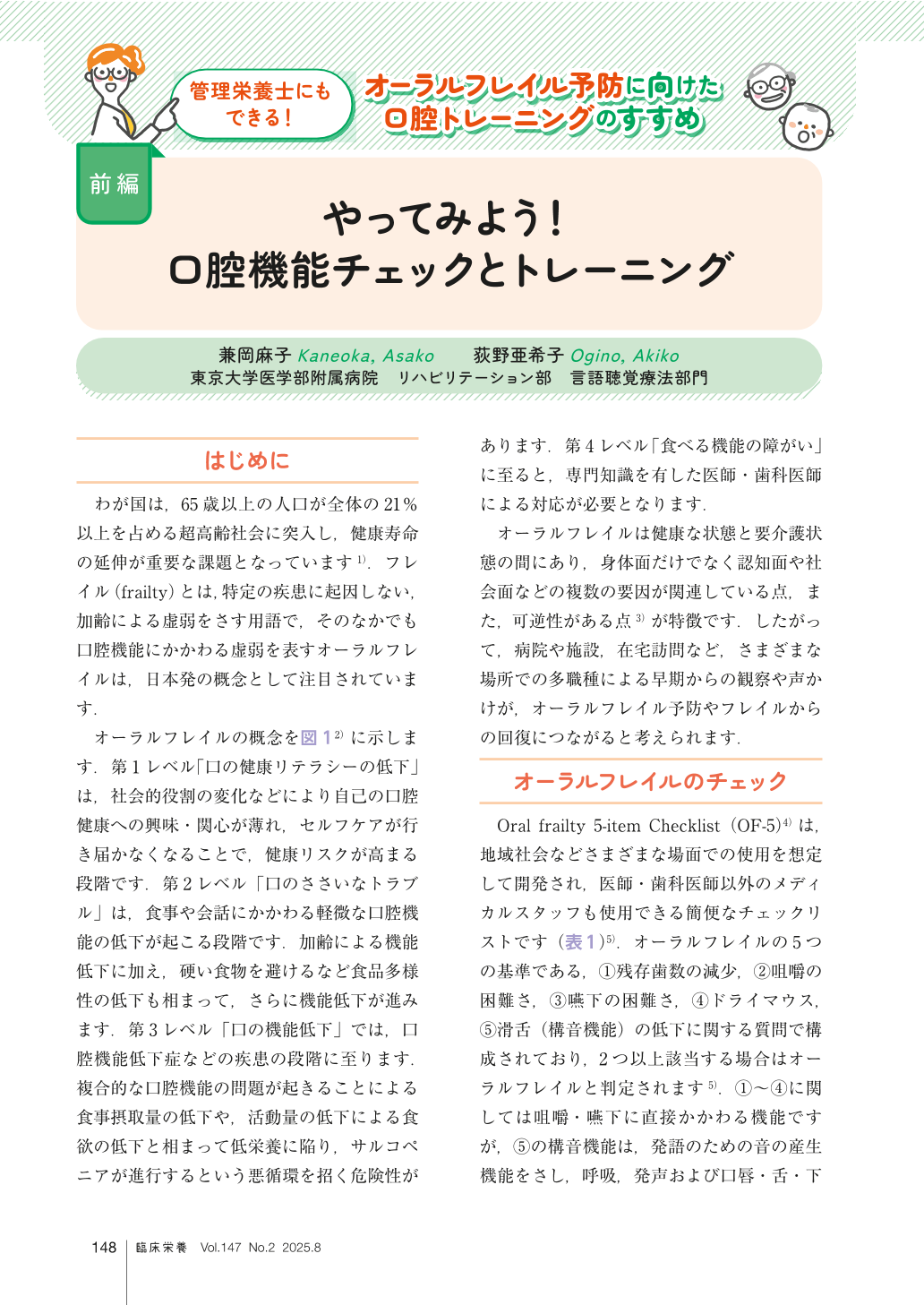
Copyright © 2025 Ishiyaku Pub,Inc. All Rights Reserved.


