特集 周産期メンタルヘルス:最新事情
各論:新生児編
2週間,1か月健診での母子愛着形成
北東 功
1
HOKUTO Isamu
1
1聖マリアンナ医科大学小児科
pp.870-873
発行日 2025年7月10日
Published Date 2025/7/10
DOI https://doi.org/10.24479/peri.0000002226
- 有料閲覧
- 文献概要
- 1ページ目
- 参考文献
- サイト内被引用
はじめに
出生直後から生後1か月にかけての親子関係は,ヒトの発達過程においてきわめて重要である。この時期における母子間・父子間の相互作用は,単なる生得的本能によって自動的に成立するものではなく,社会的学習および文化的支援の影響を強く受けながら形成される。かつては,大家族であり祖母や子育てをしている姉がいた他,近隣の知り合いに至るまでが,授乳や抱き方,沐浴,おむつ交換からあやし方,子どもとの関わり方などを教え合っていた。しかし近年では,核家族化や近隣との関わりの希薄化が進み,こういったことを「教えてもらう制度」が崩壊してしまった。現在は入院中に助産師や看護師から授乳を含めた子どもの世話を教わる他に,「近所の人たち」に変わってインターネットで得られることが子育て手技についての情報源となっている。しかし,母子の関係性については,育児マニュアルやWebで学ぶものではなく,経験や対人関係のなかから実感を伴いながら形成されていく側面が強い。また,父親も育児に参加できるように制度が変更されてきているが,父子関係についてはさらに形成が困難である。これまでの父親像とは異なる役割を果たす必要があり,「稼ぐ人」から「育てる人」への転換が求められているためである。この変化は,単に家族と時間を共有すること以上に,情緒的な関与や応答性を父親に求めるものである。しかし,育児を経験する機会が乏しかった自分の父親世代をロールモデルにできないなかで,どう振る舞えばよいかわからず,距離を感じる父親は多い。さらに,社会的にも「育児に関わる父親」に対する支援や評価が不十分であるため,努力が可視化されにくく,疎外感や無力感を抱きやすい。
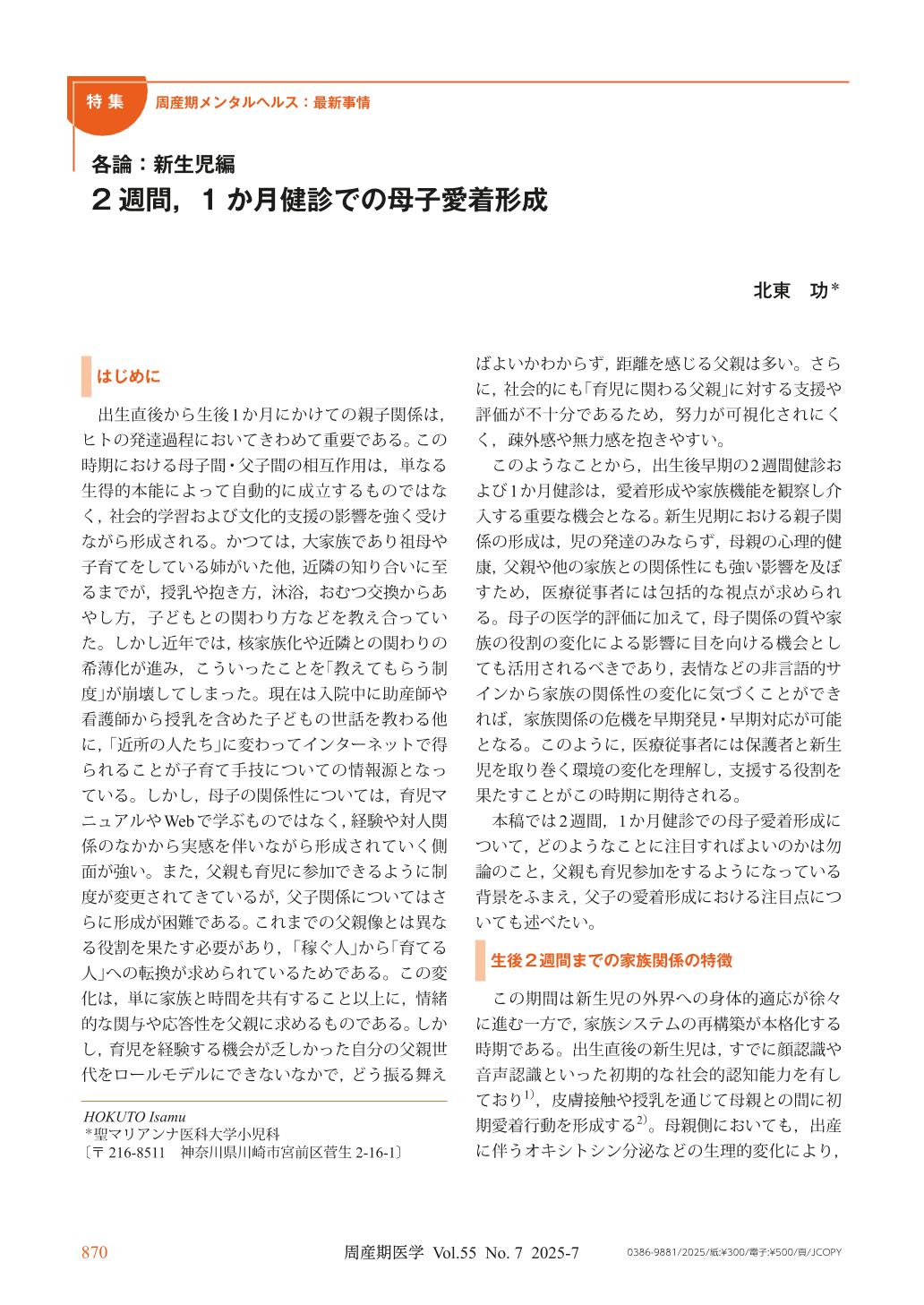
© tokyo-igakusha.co.jp. All right reserved.


