- フリーアクセス
- 文献概要
- 1ページ目
- 参考文献
この「内科」誌においては毎年1回の割合で血液疾患関係の特集が企画される.一昨年は「血栓・止血の異常を理解する」,昨年は「広く浅く知る白血病」をテーマとしたが,今回は大きく趣向を変えて「クリニック・在宅で診る血液疾患」を取り上げた.鉄欠乏性貧血以外の血液疾患の多くは,急変のリスクが高かったり,化学療法,輸血などの治療を必要としたりと,クリニックや在宅診療においては敬遠されることが多かった.実際,厚生労働省が公表している「主たる診療科,施設の種別にみた医療施設に従事する医師数及び平均年齢」のデータで病院の医師数と診療所の医師数を比較すると,平成30年12月時点では循環器内科は10,620人vs. 2,112人(5.0対1),消化器内科は11,349人vs. 3,549人(3.2対1)であるのに対して,血液内科は2,717人vs. 20人(135.9対1)と極端に診療所の医師数が少なかった1).しかし,病院における血液内科医師の激務は続き,働き方改革の実現は非現実的である.また,血液内科を志す医師の将来のキャリア選択の幅が増えるという観点からも,クリニックでの血液疾患診療の拡大は不可欠である.上記のデータから4年が経過した令和4年12月,血液内科医師数は2,948人vs. 39人(75.6対1)と診療所医師数がほぼ倍増した2).また,診療所血液内科医師の平均年齢が60.6歳から55.7歳に低下し,女性比率は15%から28%に上昇している1,2)ことから,この数年の間に若年医師,とくに女性医師の参入が進んだことがわかる.保険診療制度を含めたさまざまな障壁があるなかで,血液疾患をクリニック・在宅で診るチャレンジが広がっていることがみてとれる.そして,現在,日本血液学会としてもこの動きをサポートするために,「血液疾患の地域医療・在宅医療連携ワーキングループ」が2022年に発足して,学会として国にアプローチする試みを開始した.
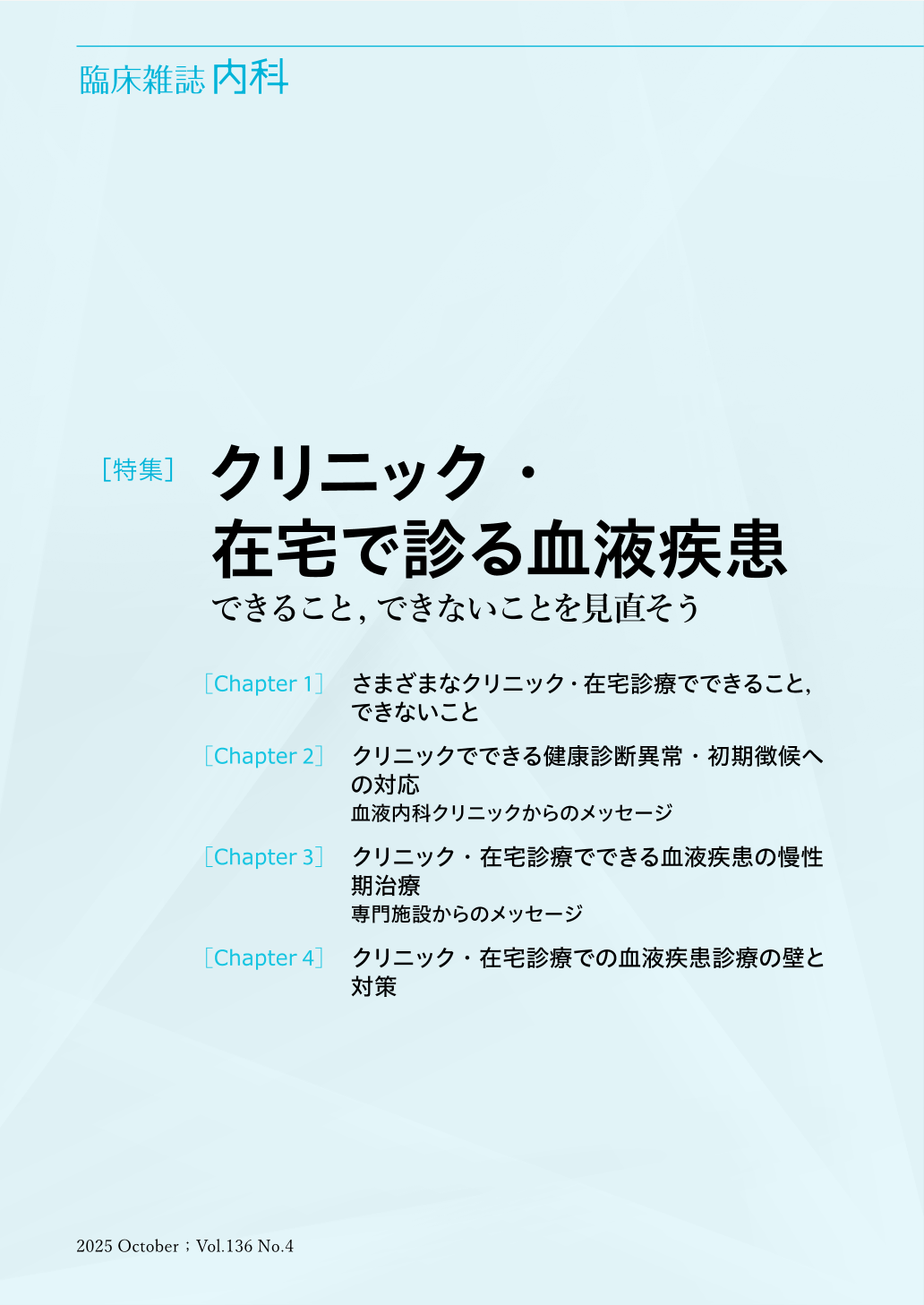
© Nankodo Co., Ltd., 2025


