- 有料閲覧
- 文献概要
- 1ページ目
- 参考文献
■はじめに
社会の高齢化は医療介護そして生活の複合ニーズを持った高齢患者の増加を意味する.このような社会環境の変化を受けて,全日本病院協会会長の神野正博氏は「患者が入院する前後のニーズにも配慮すること」の必要性を強調し,そして,そこに着目することで病院は新しいソーシャルビジネスのチャンスをつかむことができると指摘している1).ここで,厚生労働省が公開した図表1を見てみよう2).
一般病床も療養病床も稼働率が低下し,そして医業利益率も低下している.これに対して病院側からは,診療報酬の低さが原因であるという大きな批判が出ている.日本と同様の社会保険制度を持っている諸外国と比較したとき,日本の入院医療収益は確かに低い.しかし,図表1の中央のグラフは診療報酬の低さだけでは説明できない.なぜならば,団塊の世代の高齢化に伴って,入院や入所を必要とする状態像の高齢者は増加しているからである.また,介護老人保健施設や介護老人福祉施設も,利用率が低下し,赤字基調になっていることが報告されている.このことは,従来,入院や入所でケアされていた高齢者が,別の場所でケアされるようになっていることを示唆している.恐らく,それはサービス付き高齢者向け住宅(以下,サ高住)や有料老人ホームであり,そこに外付けで医療や介護が提供されることで,入院や入所と同様のサービスが提供されているのである.しかし,それがどのような質のサービスであるかについては,医療保険,介護保険で収集している情報では分からない.玉石混交というのが実際のところだろう.一部の営利的なサービス提供体があることは報道などで明らかになっているが,それをもってそのようなサービス形態全体が問題であるという議論の持ち方は正しくない.むしろ,そのようなサービス形態が広く利用者から受け入れられているという事実に,病院関係者は注目する必要がある.
今回は,上記の問題に答えるために福岡県久留米市で高良台リハビリテーション病院を中核施設として,シニア住宅や特別養護老人ホーム,在宅支援サービスなど,医療・介護・福祉サービスを包括的に展開する医療法人社団久英会(以下,久英会)を取り上げる.
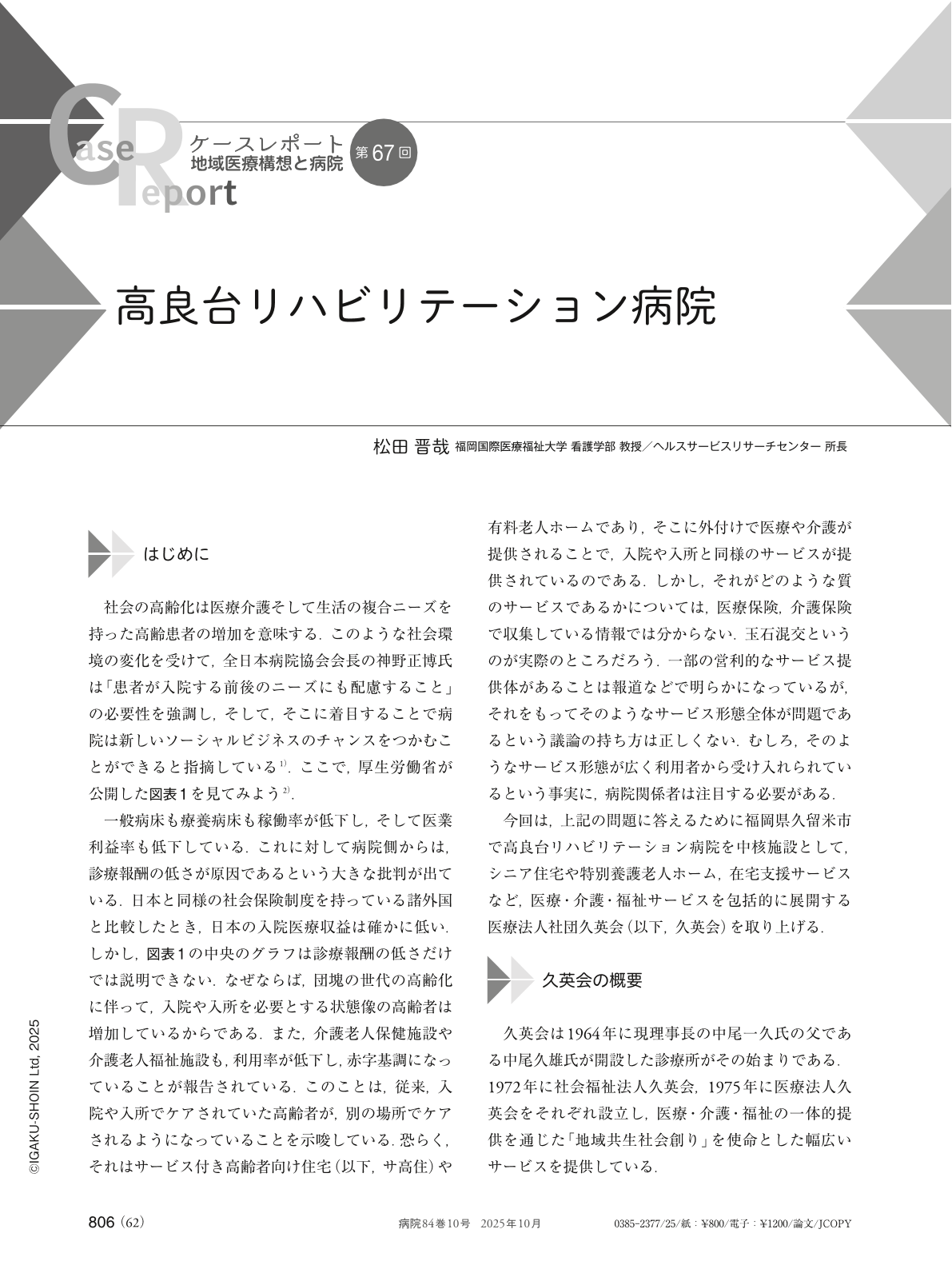
Copyright © 2025, Igaku-Shoin Ltd. All rights reserved.


