- 有料閲覧
- 文献概要
- 1ページ目
- 参考文献
はじめに—One Healthと人獣共通感染症
令和3年(2021年)1月に日本で始めてOne Healthに関する条例(「福岡県ワンヘルス推進基本条例」1))が制定され,最近日本でも“One Health”という言葉をよく耳にするようになった.One Healthの概念は,“ヒトと動物,環境の健康は相互に密接な関連がある”という前提のもと,これらを一体のものとして守るための分野横断的な考え方を意味している.
一方で,人獣共通感染症は読んでその名の通り,同一の病原体によってヒトとヒト以外の動物(脊椎動物)の両方で疾患が引き起こされる感染症である.人獣共通感染症はヒト感染症の約60%を占めるとも言われている.重症急性呼吸器症候群(severe acute respiratory syndrome:SARS),エボラウイルス病,変異型クロイツフェルト・ヤコブ病(いわゆる“狂牛病”),鳥由来インフルエンザウイルス感染症,COVID-19など,社会的インパクトの大きな感染症が,動物からヒトへともたらされた病原体によって引き起こされている.
One Healthの歴史は古く,“zoonosis(人獣共通感染症の英訳)”という言葉を作ったドイツの医学者Rudolf Ludwig Karl Virchow博士が“医学と獣医学のあいだに境界線はない”と提唱したことに端を発している.“One Health”という言葉自体は,その後2004年になって米国のロックフェラー大学で野生生物保全協会が主催した国際シンポジウムに由来している(“One World, One Health”).この会議では「マンハッタン原則」と呼ばれる人獣共通感染症対策における12の行動原則が示され,これをもってOne Healthの概念が明確なものになったと考えられている.より近年では2021年のG7カービスベイサミットで採択された「カービスベイ保健宣言」,2023年のG7保健大臣会合で採択された「長崎保健大臣宣言」でも,One Healthの重要性が盛り込まれており,国際的にもますます重要な概念として認知されている.
当初,人獣共通感染症対策を念頭に置いて成立したOne Healthの概念は,現在では我々を取り巻く環境の健康も含めた“保全医学”の考え方や,ヒトと動物の病気の共通性から双方の疾病の対策に取り組む“zoobiquity(汎動物学)”,さらにはヒトと動物の関係性(human-animal bond)を考える動物福祉の考え方を取り込み,進化し続けている.本稿では,人獣共通感染症におけるOne Healthを考える一例として米国におけるウシの高病原性鳥インフルエンザウイルス感染例を取り上げ,事例概説することで,読者諸氏がOne Healthについて考える一助となればと思う.
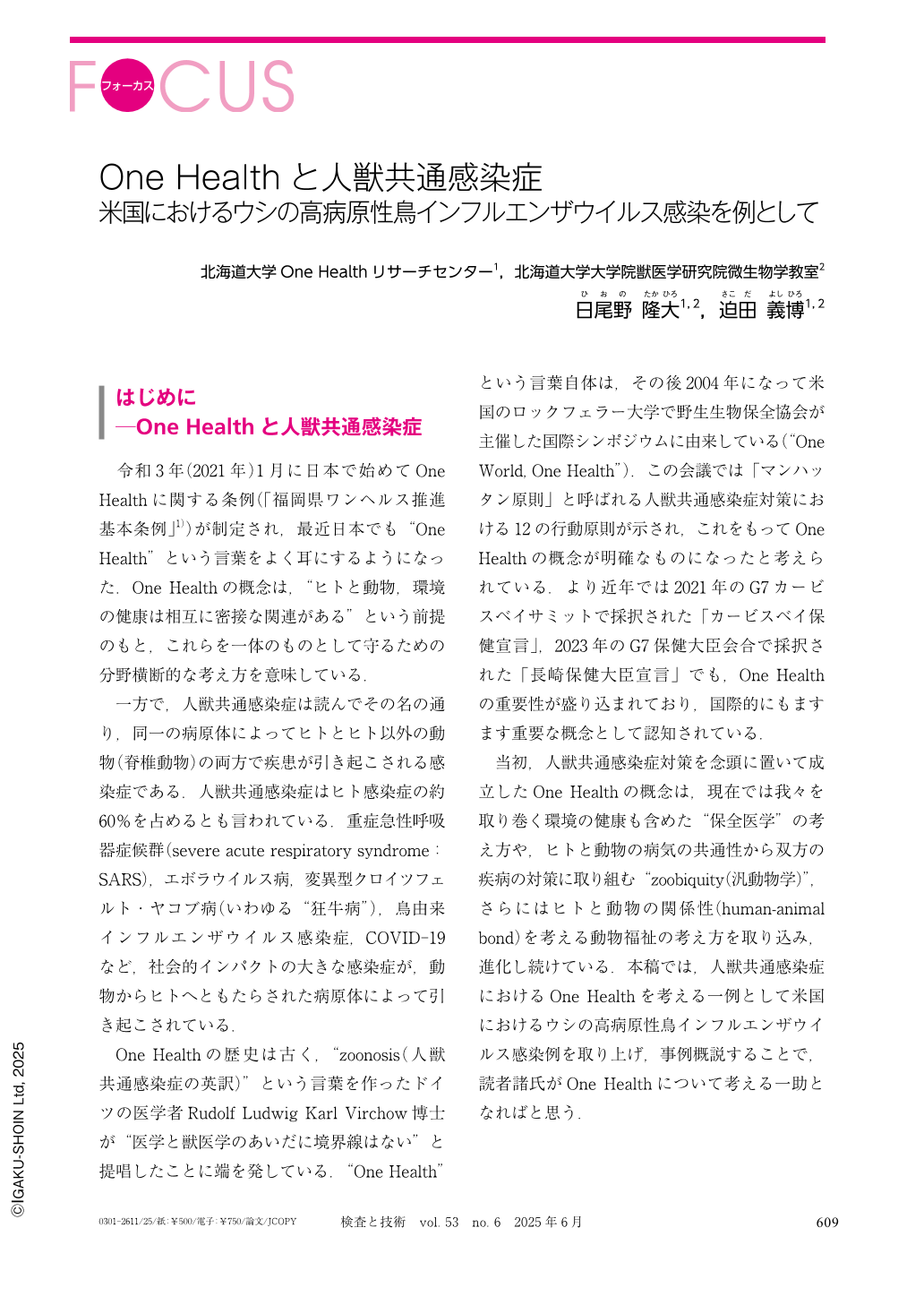
Copyright © 2025, Igaku-Shoin Ltd. All rights reserved.


