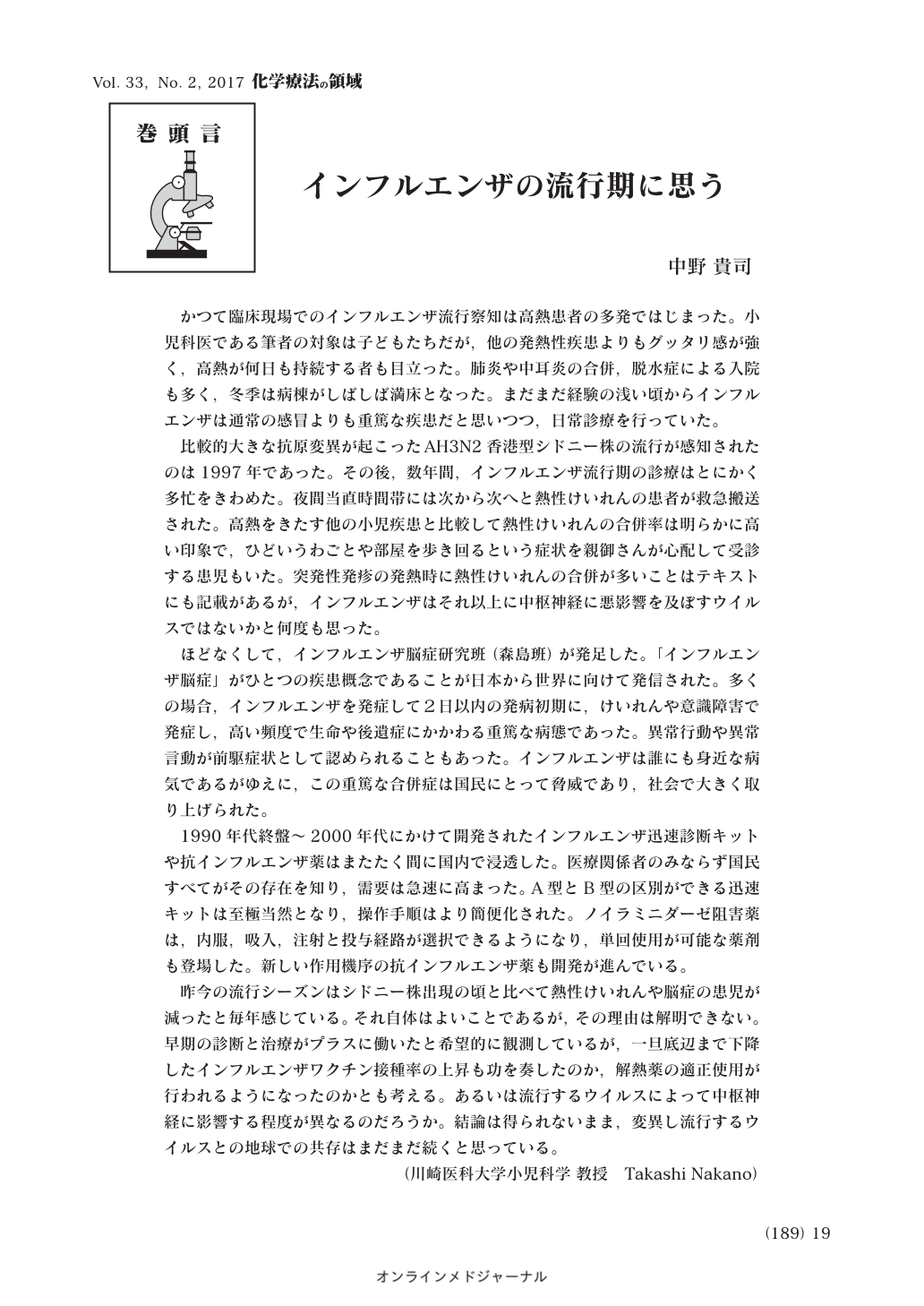- フリーアクセス
- 文献概要
- 1ページ目
かつて臨床現場でのインフルエンザ流行察知は高熱患者の多発ではじまった。小児科医である筆者の対象は子どもたちだが,他の発熱性疾患よりもグッタリ感が強く,高熱が何日も持続する者も目立った。肺炎や中耳炎の合併,脱水症による入院も多く,冬季は病棟がしばしば満床となった。まだまだ経験の浅い頃からインフルエンザは通常の感冒よりも重篤な疾患だと思いつつ,日常診療を行っていた。 比較的大きな抗原変異が起こったAH3N2香港型シドニー株の流行が感知されたのは1997年であった。その後,数年間,インフルエンザ流行期の診療はとにかく多忙をきわめた。夜間当直時間帯には次から次へと熱性けいれんの患者が救急搬送された。高熱をきたす他の小児疾患と比較して熱性けいれんの合併率は明らかに高い印象で,ひどいうわごとや部屋を歩き回るという症状を親御さんが心配して受診する患児もいた。突発性発疹の発熱時に熱性けいれんの合併が多いことはテキストにも記載があるが,インフルエンザはそれ以上に中枢神経に悪影響を及ぼすウイルスではないかと何度も思った。 ほどなくして,インフルエンザ脳症研究班(森島班)が発足した。「インフルエンザ脳症」がひとつの疾患概念であることが日本から世界に向けて発信された。多くの場合,インフルエンザを発症して2日以内の発病初期に,けいれんや意識障害で発症し,高い頻度で生命や後遺症にかかわる重篤な病態であった。異常行動や異常言動が前駆症状として認められることもあった。インフルエンザは誰にも身近な病気であるがゆえに,この重篤な合併症は国民にとって脅威であり,社会で大きく取り上げられた。 1990年代終盤~2000年代にかけて開発されたインフルエンザ迅速診断キットや抗インフルエンザ薬はまたたく間に国内で浸透した。医療関係者のみならず国民すべてがその存在を知り,需要は急速に高まった。A型とB型の区別ができる迅速キットは至極当然となり,操作手順はより簡便化された。ノイラミニダーゼ阻害薬は,内服,吸入,注射と投与経路が選択できるようになり,単回使用が可能な薬剤も登場した。新しい作用機序の抗インフルエンザ薬も開発が進んでいる。 昨今の流行シーズンはシドニー株出現の頃と比べて熱性けいれんや脳症の患児が減ったと毎年感じている。それ自体はよいことであるが,その理由は解明できない。早期の診断と治療がプラスに働いたと希望的に観測しているが,一旦底辺まで下降したインフルエンザワクチン接種率の上昇も功を奏したのか,解熱薬の適正使用が行われるようになったのかとも考える。あるいは流行するウイルスによって中枢神経に影響する程度が異なるのだろうか。結論は得られないまま,変異し流行するウイルスとの地球での共存はまだまだ続くと思っている。