- 有料閲覧
- 文献概要
- 1ページ目
精神分裂病の研究は,E. Kraepelin以来,幾多の概念の深化や知見の集積を加えたにもかかわらず,定見の確立にいたらず,なお未知の内因性過程が容認されている。この了解不可能な内因性にもとづく病態の究明に対して,精神力動的に心理的要因ないしその発展過程の検討を主とするもの,中枢神経系の生理学,生化学,薬理学などの知見を実験的にも症例的にも追究せんとするもの,および精神的身体的症状を統一的に人間現存在の世界内存在のありかたの偏倚としてそのまま深い人間理解に到達しようとする人間学的立場などが考えられるが,これらの知見について1941年から1950年における精神分裂病研究の綜説のなかで,M. Bleulerは,患者の個々の人格と疾患経過が注目されるべきで,その根底にはなんらかの生活過程の困難が想定されえ,これが,古典的,記載的な態度の代わりに,説明心理学的に追求されるようになることを主張している。このような態度は1952年以来,DelayおよびDenikerによるPhenothiazine誘導体を初めとするNeuroplegicaの精神科疾患への応用により,治療の便宜ないし促進に加えて,分裂性病態の詳細な観察が容易となるにつれ,ふたたび経過が短く予後の良好な病態を問題とすることになる。これは精神分裂病という不治性を本質とする概念が,これらの予後の良好な病態に適当かという問題からであり,B. PauleikhoffやJ. E. Staehelinはこの忌なまるべき予後を意味する診断名にできるだけ慎重であることを主張し近縁な病態の鑑別的操作のなかにかえつて内因性病態の要因を究明しようとする。著者のF. LabhardtはこのStaehelinの弟子であり,師の間脳一中脳障害の精神病理学,Emotionspsychose,Praeschizophrene Somatose,あるいは精神障害における脳幹植物性中枢の意義などの研究とも関連しつつ,薬物療法による関与の立場から精神分裂病および他の精神疾患の病態を数編の論文において鋭意追究してきたものであり,脳生理学的立場も重視するとともに,精神的要因に対しても深い関心が認められる。著者はE. Kretschmerの多元的診断の態度を強調し,これはもともと診断にさいして種々のpathogenetisch,pathoplastischな要素が評価されねばならぬとする立場であり,とくに現代の生活の複雑化された様相の下にあつては,遺伝,素因のほかに,さらに環境,情動性,心的・身体的要因,薬物の乱用,中毒などが慎重に考慮されねばならぬとする。そしてこのEmotionspsychoseに関しては,経過が短かく予後のよい,全経過のはつきりした病像が,この多元的観点にもとついて明確に解明されており,さらに近縁病態との関連性も検討されて,これらによりなお規定されない分裂病の謎が却つてここに浮き彫りされている。副題には「分裂病様病態像の鑑別への寄与」がうたわれているが,ここに収録されたEmotionspsychose 53例の資料は,広く分裂性病態研究のみすごしえぬ知見を提供していると思われる。
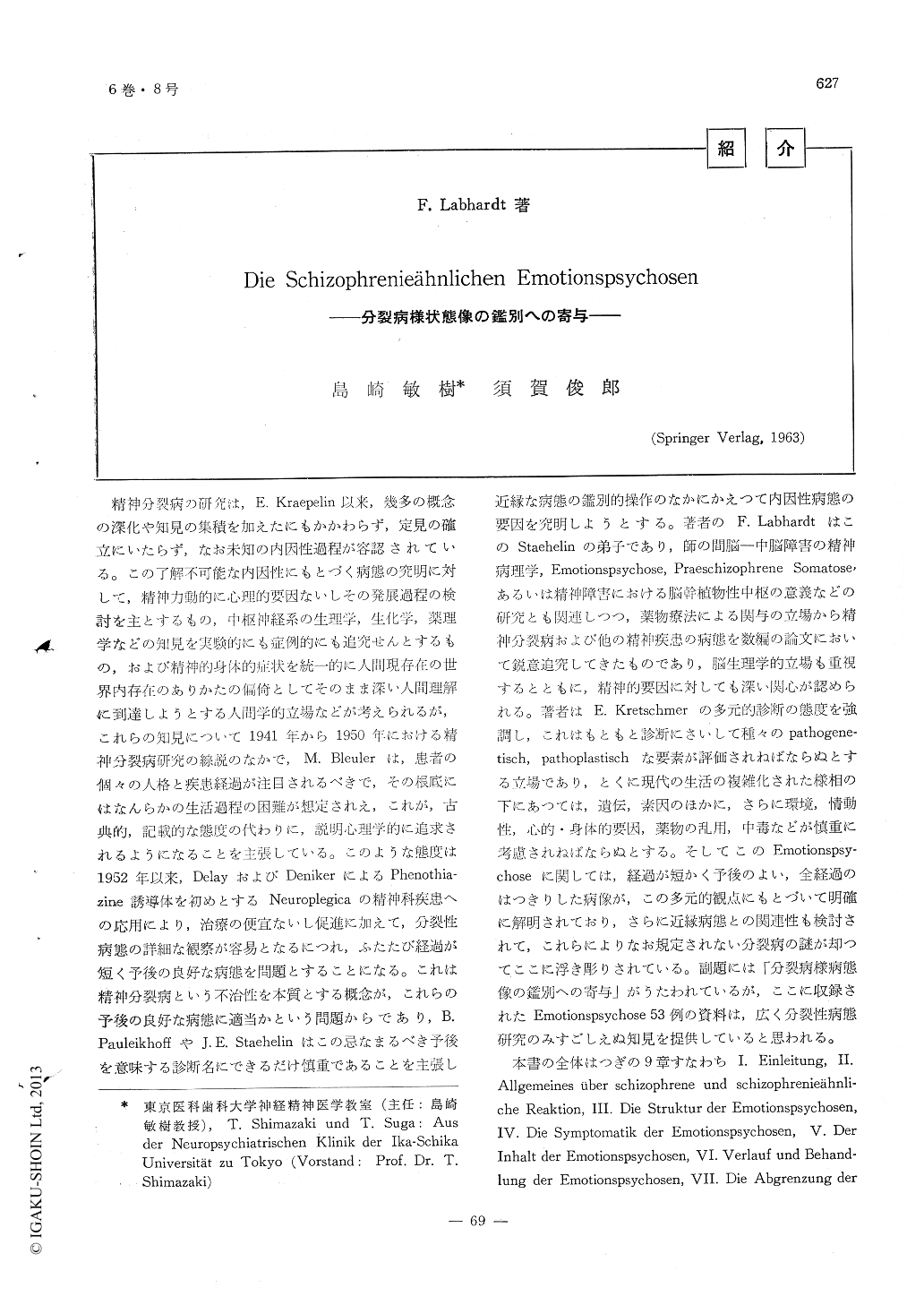
Copyright © 1964, Igaku-Shoin Ltd. All rights reserved.


