- 有料閲覧
- 文献概要
- 1ページ目
- 参考文献
はじめに
自殺は、その多くが追い込まれた末の死であるといわれている。自殺の背景には、精神保健上の問題だけでなく、過労、生活困窮、育児や介護疲れ、いじめや孤独・孤立などのさまざまな社会的要因があることが知られている。自殺は、人が自ら命を絶つ瞬間的な行為としてだけでなく、人が命を絶たざるを得ない状況に追い込まれるプロセスとして捉える必要がある。
わが国の自殺者数は、1998(平成10)年に前年から8,472人増加の3万2,863人と3万人を超え、2003(平成15)年には統計を取り始めた1978(昭和53)年以降で最多となる3万4,427人となるなど、毎年3万人を超える方が自殺により死亡する状況が続いていた。このような状況に対処するため、2006(平成18)年に自殺対策基本法が成立し、その翌年には政府が推進すべき自殺対策の指針である自殺総合対策大綱(以下、大綱)が策定された。自殺対策基本法が成立した2006(平成18)年と、コロナ禍以前の2019(令和元)年の自殺者数を比較すると、男性は38%減、女性は35%減となっており、これまでの取り組みに一定の効果があったと考えられる(2006〔平成18〕年:3万2,155人→2019〔令和元〕年:2万169人)。しかし、自殺者数は依然として毎年2万人を超える水準で推移しており、さらに新型コロナウイルス感染症(COVID-19)流行の影響で自殺の要因となるさまざまな問題が悪化したことなどにより、2020(令和2)年から女性の自殺者数は増加、小中高生は過去最多の水準となっていた(図1)1)。
日本において孤独や社会的孤立は、少子高齢化や都市部への人口集中、核家族化などの影響で拡大しつつあり、近年特に深刻な課題として認識されている。こうした問題は精神的健康に重大な影響を及ぼし、生活の質を低下させるだけでなく、自殺リスクを高める危険因子とされている2)。「孤独」は主観的な精神状態であり、「孤立」は他者とのつながりが乏しい客観的状態を指す。これらは人間関係や経済的困難が原因となり、健康や生活に悪影響を及ぼす懸念があるため、孤独・孤立の双方に対応する施策が求められる。公的な関与は個人の領域を尊重しつつ、望ましくない孤独・孤立を対象とし、実態に基づいた支援が行われるべきである。目指すのは、誰もが取り残されない社会、自己存在感とつながりを感じられる社会であり、悪影響が連鎖しないよう、社会全体で支え合う体制が必要とされる。さらに、支援を求めやすい環境づくりとして、ポータルサイトや24時間対応の相談体制が整備され、行政と民間が連携して包括的な支援体制の構築に努める必要がある。NPO等との協力も重視され、支援の質向上を図り、行政と民間が一体となり孤独・孤立対策を推進することが求められている3)。
こうした背景を踏まえ、「孤独・孤立対策推進法」が成立し、厚生労働省では「孤独・孤立対策のための自殺防止対策事業」を展開するなどして、孤独・孤立に悩む者が支援を受けられる体制づくりを進めている。本稿では、厚生労働省において実施している、孤独・孤立対策および関連した自殺防止対策事業等について概説する。
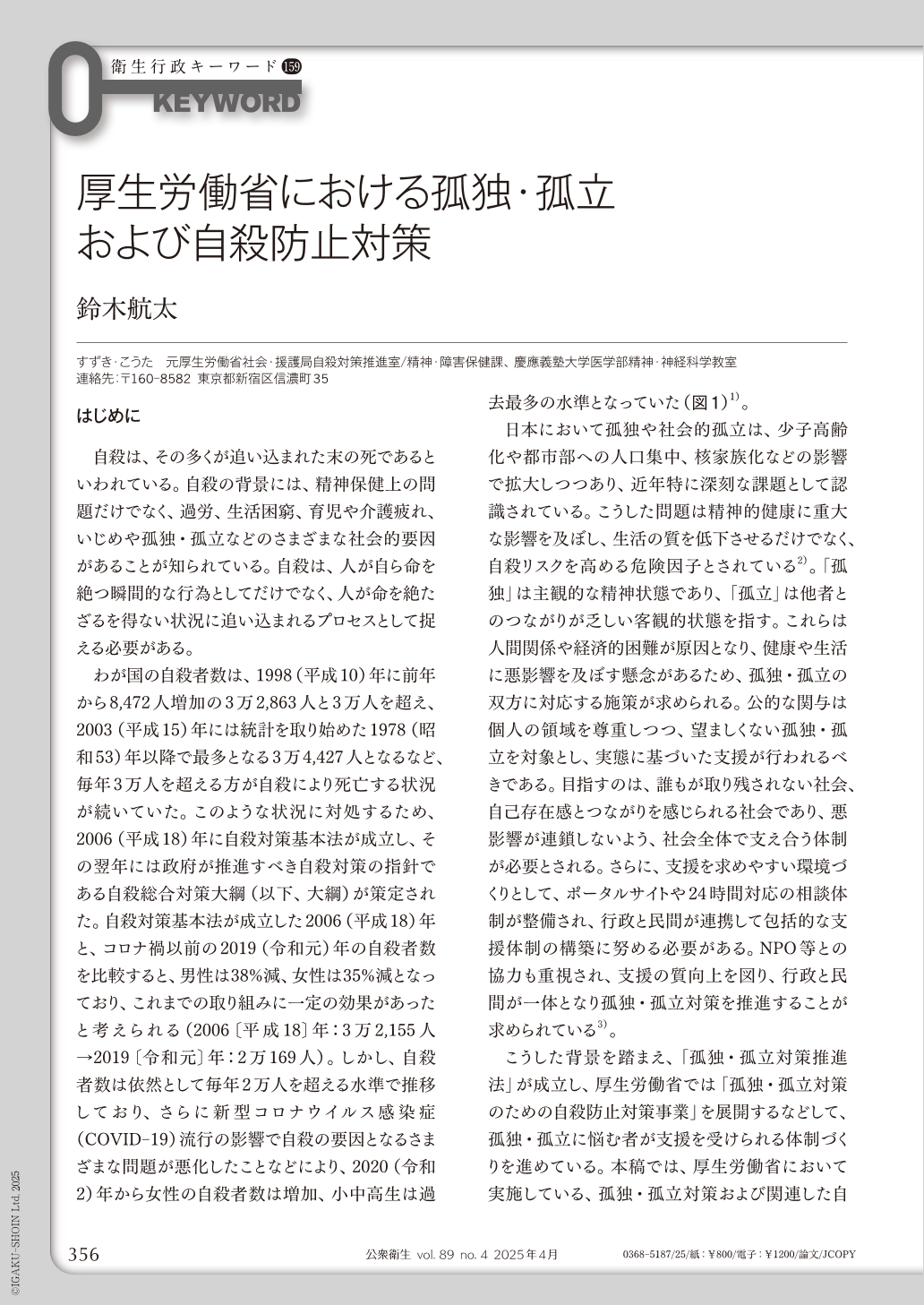
Copyright © 2025, Igaku-Shoin Ltd. All rights reserved.


