- フリーアクセス
- 文献概要
- 1ページ目
現在,炎症性腸疾患(IBD)に対する内科治療の進歩により,内科治療抵抗を理由に外科手術が選択される症例は減少しつつある.一方で,長期経過例の増加により必然的にIBD関連腫瘍の早期発見を目的としたIBD患者のトータルマネージメントの重要性が高まっている.炎症性発癌のリスク管理において,適切なサーベイランスの実施が必須であることは言うまでもないが,IBD関連腫瘍は孤発性腫瘍に比べて早期発見が困難であることが大きな課題である.潰瘍性大腸炎(UC)では,内視鏡機器の進歩に伴い早期発見例が増加しており,境界明瞭なlow-grade dysplasiaに対しては内視鏡切除が治療法の選択肢となりうるが,異時性多発病変や内視鏡では病変指摘が困難な症例も存在するため,十分なコンセンサスが得られていない.一方,Crohn病(CD)においては,腸管合併症などにより内視鏡検査が困難な症例が少なくないことや,肛門部癌の比率が高いことなどから,サーベイランスの方法自体が模索段階にある.このような背景を踏まえて,本特集号では「炎症性腸疾患関連腫瘍の最前線」をテーマに,本領域のエキスパートの先生方より最新のエビデンスを踏まえて執筆をいただいた.
序説(江﨑論文)では,IBD関連腫瘍の診断・サーベイランスに関する現状と課題を整理いただいた.下田論文では,IBD関連腫瘍の病理組織学的特徴と病理診断用語・分類・基準について大変わかりやすく解説されており,臨床医の先生にはぜひご一読いただきたい.岡田論文では,UCサーベイランスの概念から始まり,リスク別のサーベイランス間隔,外科手術後の予後,回腸囊サーベイランスの必要性など,外科医の視点から多角的なサーベイランスの重要性を示された.福田論文では,UC関連腫瘍の内視鏡診断を中心に,存在診断,質的診断,異型度/深達度診断別に現状と課題について,多数の症例を提示し解説いただいた.異所性多発病変の存在診断が今後の課題であることが明らかと言える.梁井論文では,SCENIC国際コンセンサスを踏まえたUC関連腫瘍に対する内視鏡治療の適応について,各ガイドラインを触れたうえで,本邦のESD報告例から異時性再発の管理を含めた内視鏡治療の妥当性について長期的観点から明らかにしていく重要性を示していただいた.横山論文では,CD関連腸管腫瘍画像診断の現状と課題について,実際の症例を提示いただきわかりやすく解説いただいた.高橋論文では,CD関連肛門管癌に対するサーベイランスの現状と課題について自施設の取り組みも含めて解説いただいた.CD関連肛門管癌の早期診断は困難であり,治療可能な病期での診断を目指す,のが現実的な目標となっており,早期発見のためにさらなる工夫が必要であろう.
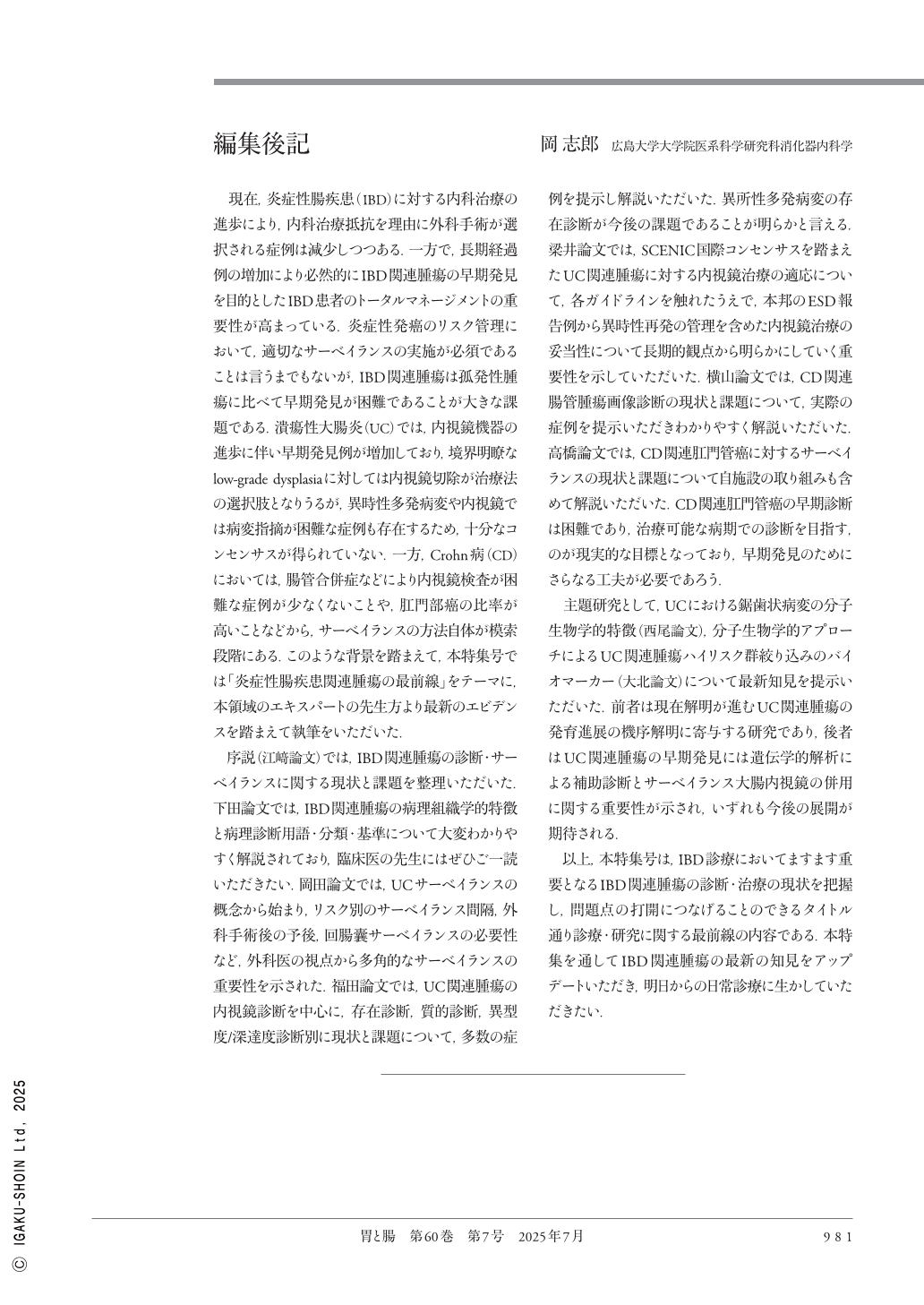
Copyright © 2025, Igaku-Shoin Ltd. All rights reserved.


