連載 人間はいつから病気になったのか─こころとからだの思想史[2]
誰のものでもない体
橋本 一径
1
1早稲田大学文学学術院
pp.198-202
発行日 2016年2月15日
Published Date 2016/2/15
DOI https://doi.org/10.11477/mf.1430200067
- 有料閲覧
- 文献概要
- 1ページ目
- 参考文献
「病気」とは何か
「病人」と「病気」は、かつては分かちがたく結びついていた。すなわち当人が痛みなどの症状を自覚し、「病人」になるところからしか、「病気」は始まらなかった。ところが診断技術などが進化するにつれて、「病気」とは、時として本人の自覚に先立って、医師により見いだされるものとなった。「病人」と「病気」とが乖離し、人間は、自分が「いつから病気になったのか」、自分ではわからなくなってしまったのだ。ここまでが前回で確認したことである。
では「病人」よりも医師のほうが「病気」の発見に長けているとするなら、医師は発見したその「病気」を、当人が認めようが認めまいが、さっさと治療してしまえばよいのではないか。まだ自覚症状のない者にとって、自分が「病人」であるのを認めるというのは、困難な作業である。時には自分が「病人」であることをかたくなに認めようとしない患者もきっといることだろう。そんな患者の説得のために時間をやみくもに割くよりも、手術台に無理やり縛り付けて治療を済ませてしまったほうが、結果として当人のためになる場合もあるのではないか?
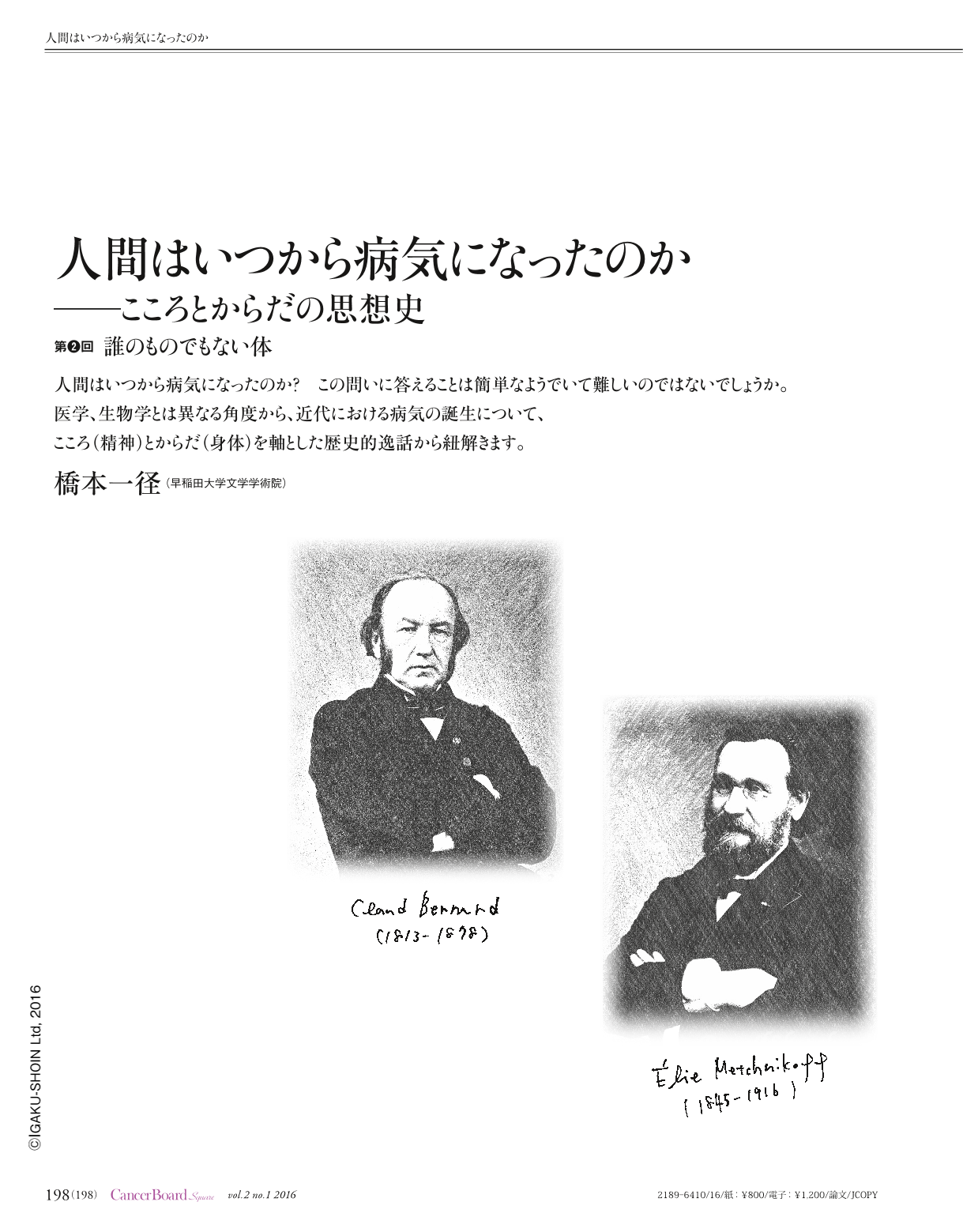
Copyright © 2016, Igaku-Shoin Ltd. All rights reserved.


